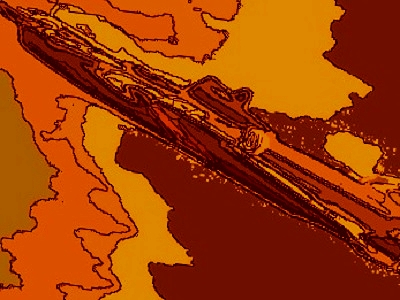 交差点を急角度で曲がっていくセダンの後部座席で、矢吹郷之助は肩に食い込んでくるシートベルトが不快だった。運転する川上登は不意に現れた不審車を撒こうとしたのだが、追手は執拗に喰いついてくる。そろそろ朝の通勤時間帯になる。矢吹は一つ先の交差点で路地に入るよう指示した。
交差点を急角度で曲がっていくセダンの後部座席で、矢吹郷之助は肩に食い込んでくるシートベルトが不快だった。運転する川上登は不意に現れた不審車を撒こうとしたのだが、追手は執拗に喰いついてくる。そろそろ朝の通勤時間帯になる。矢吹は一つ先の交差点で路地に入るよう指示した。
「路地の左手にコインパーキングがある。そこへ駐車したまえ。まわりの通行に迷惑をかけてはいられん」
「しかしあいつらQの一味ですよ。停まれば危険です」
セダンは東銀座から路地に入り新橋方面へと駆け抜け、矢吹が告げた時間貸し駐車場へとドリフトしながら滑り込む。1.5車線程度の路地では運転している川上自身が背中に冷たいものを浴びる気分だったが、彼のテクニック以上に奇跡でも起きているのか、路傍のポリバケツを吹き飛ばした程度で済んでいた。
矢吹は既に「ガリレー」の店番をしている弓田エマに電話をかけていた。
「そうだ、裏にいるから『あれ』を持って出てきておくれ」
そこへ路地に急停車した追手がドアを蹴破るように開けて飛び出してきた。三人だ。そのうちの一人がやにわに拳銃を突き付け窓ガラス越しに川上を威嚇する。矢吹は「何事かね」とつぶやきながら自分の座席の窓を降ろした。
「会長、なにを!」
開いた窓に目がとまり、追手はすぐさま後部座席側へ駆け寄った。その瞬間、車内から細いワイヤーが二本放たれ追手の胸に先端の金属が突き刺さる。追手は不意に痙攣したかと思うとはじけ飛ぶように崩れ落ちた。
勢いで外れたワイヤーは自動的に矢吹の持つ携帯電話へ巻き戻された。
「は・・・一回の放電で電池切れだよ」
「窓を閉めてください、まだ二人います」
あとに続いてきた二人はさすがにセダンと距離を置きながら発砲する。消音機をつけたハンドガンだ。人通りのない路地では銃撃に気づく者もいない。
だが、路地に建ち並ぶビルとビルの間から飛び出してきたエマが何か叫びながら赤い筒のようなものを突き出すのが川上には見えた。エマは筒の先端の蓋を跳ね上げ、隠しスイッチを押し込む。彼女の腕が少し持ち上がるほどの圧力を開放しながら、消火器の粉末のような勢いで蒸気が噴き出す。
二人の追手は高熱の蒸気を浴びてひるむがそれだけでは済まなかった。筒からは蒸気に続いて電撃が走り、追手を悶絶させてしまう。
「ご無事ですか会長」
エマはセダンのドアを開けて矢吹を外に連れ出す。川上も車外に出る。
「スタンポット。意外と使えるね」
「手袋していてもピリピリしましたわ。絶縁が不十分です」
「こいつら、どうしましょうか」
「これに限っては私を襲う意図がわからんが捨ておきなさい。今はそれどころではない」
「会長、パンパスの準備はできています。お急ぎください」
エマは矢吹と川上を案内して喫茶店ガリレーの裏口に向かう。
ガリレーは喫茶店と古地図屋を掛け持ちする、当八郎が経営する店舗だ。普段は一条マリがカウンターに入っている。一般客が皆無というわけではないが、常連のほとんどがマイティジャックのメンバーだ。当は地図屋でもありアルピニストでもあるが、日常のなりわいはこの店にある。
「お客には悪いが、今日からしばし臨時休業だ」
矢吹は川上に後方を護衛されながら店内に入るが、彼自身もコーヒーを注文する時間を得られなかった。
「まったく、50年代や60年代のスパイ映画じゃあるまいし、銃撃など無粋な連中だよ」
「会長こそ仕込みスマホとは今風じゃないですか。窓を開けられたときは焦りましたよ」
「直撃でないと効き目が無いのでね。村上君の作品だが、なんでこうも電話以外の機能がもてはやされるのか」
ガリレーのバックヤードにはロッカーに偽装されたエレベータが存在する。大深度地下に降りると、リニアモーター式モノレール・パンパスが待機しており、銀座のはずれから一気に三浦半島のMJ号ドックまで隊員を搬送する。東京の地下鉄網が発達しながらも新規路線が大江戸線以降実現していないのは、この秘匿路線にそろそろ引っかかる懸念が出ているための、矢吹コンツェルンの時間稼ぎとも、MJの間では噂となっている。
「さて本部に着くまでにやれることは何かな。Q衛星兵器は久里浜から上総湊にかけての浦賀水道を凍らせたというが」
「30分で三発、東京湾内への艦船進入ができなくなっているそうです。今現在、伊良子岬付近にも着弾したとか」
「ちくしょう、港湾機能の麻痺を狙っているのか」
Qの『熱い氷』は、着弾の直後は液体を500℃にまで沸騰させ、その後急速に冷却して個体化する。文字通りの凍結なのだが融点は異常に高く、水の場合移相融点である100℃では解凍できなくなってしまう。
浦賀水道をこの手で封鎖されると、東京湾内の主要重要港湾、海上保安庁、海上自衛隊、アメリカ海軍のすべてが封じ込められてしまうのだ。
「おそらく次は原発周辺の海域も撃たれるだろう。MJ号はまんまと誘き出されたというわけだ」
「会長のご指示通り、横須賀地方総監部には連絡済みです。演習名目で掃海隊が出てくれるそうです」
「承知した。例の『稲妻落とし弾』は引き渡しできたかね」
「村上さんからの報告で急ごしらえした得体のしれない弾頭なので、上に渋られたようですわ。いずこも現場はつらいのですね」
「気化爆弾なんぞを使うよりずっとマシだよ。そろそろ到着かな」
車両が減速する体感を得た。東京・横須賀を往来するのに最高時速500キロというパンパスだが、高齢の矢吹が乗車するため速度は「0系ひかり」並みに落とされた。それでも約70キロのルートを時速200キロで突っ走ってきた。
川上がまず座席をあとにした。
「自分は観音崎に上がって状況監視します。会長は本部に常駐して外出なさらないでください」
「そうさせてもらうよ。エマ君のコーヒーを所望しようか」
「マリさんほど上手じゃありませんよ」
東京でのひと騒動と前後する小笠原沖の排他的経済水域では、夕暮れの波間をMT号が東へ航海していた。
MJ号を内蔵するため、船体は設計段階からタンカーではなくコンテナ船に偽装されている。うず高く積み上げられたように見えるコンテナ群は二重構造のフレキシブルパネルで、MJ号の「高さ分」を稼いでいた。
船は一つ舵取りを誤れば座礁する岩礁海域に到着した。巨大なMJ号を東へ打ち上げるためには、MT号のアンカーだけでは発射基地として固定が不足する。
そのことはトーマス・ナリタの脳内でも織り込み済みで、MT号両舷前後には伸縮式のアームアンカーが装備されている。これを岩礁にあてがい船体を固定するのだ。
マイティジャックのメンバーが第二ドックに辿り着いてから、12時間が経過していた。
『10分後に偽装コンテナパネルの展開、15分後に架台のジャッキアップを開始する。仰角は80度、準備を完了させ着座せよ。発射シークエンスはそちらに委ねる』
大利根七瀬船長が段取りを伝達する。
「了解、散々世話になりました。第二ドックとMT号の皆さんに感謝します」
『当君、武運を祈る。お互い妙な星の元に生きているが、逢うことができて嬉しく思うよ』
「・・・四十手前で言うのもなんですが、私はまだ若造らしい。その言葉を素直に受け止めることがまだできそうもありませんが、噛みしめておきますよ」
その会話を耳にしたマリは首をかしげた。
「隊長たち、何の話をしているの?」
「人生いろいろあるんだろうさ。若気の至りなら私だってまだあるぞ。なあ先生?」
「博士の日常に巻き込まんでくださいよ」
村上譲と英 健が軽口をたたいてその場をごまかす中、トーマスがシークエンスを読み上げる。
「ジャッキアップに続いて両翼展開・固定。射出は翼端の補助スラスターで持ち上げます!」
「30000トン近くの船を支えられるのかいこの架台?」
「出来るわけないじゃないですかゲンさん。架台の後ろ半分を逆に海中に沈めるんですよ。見かけ上艦首は仰角を得られる寸法です」
寺川進が源田明に説明する。
「なんだよそれじゃあ打ち上げの衝撃で架台はMT号から落っこちちゃうじゃないか」
源田は呆れた顔をする。
「通常離水をなぜしないんだ?」
「さあ・・・まさかの趣味性とか」
いつものブリッジだと当は緊張の中にも安堵感を覚えた。これもまたいつものように、手持無沙汰となると右へ左へうろうろする天田一平の背中も、ブリッジ風景として欠かせないと思うのだが・・・
「副長、我慢は体に良くないぞ」
そう言われた天田は当の方へ振り返る。当はにやにやしながら「行け」と合図した。
「そうですな。そんじゃいっちょうやってくるか。天田一平、アストランダ―ウイングに搭乗します!」
バリバリと軽い音を立てて天田のブーツが床のベルクロを離れる。まだ重力下だが、彼等のブーツの靴底には無重力環境に備えてベルクロと磁石による設置対応加工が施されている。
「コンテナ開放まで5分です」
マリが時計を確認したその2分後、天田のすっとんきょうな声がブリッジ通信に伝わってきた。
『あれっ! なんでいるんだ桂君っ』
ブリッジの面々も「えっ?」という顔をして大型モニターを見やった。
パイロットスーツに身を固めた桂めぐみがにこにこしながら宇宙戦闘機「アストランダ―ウイング」の操縦席に待機していた。
『なんでって、これの操縦訓練を受けているのよあたし』
『なんだってーっ』
当はつい、笑いを抑えられずに顔をそむけたが、すぐに天田に言った。
「桂君はこの半年、横田基地に通って米空軍の専門訓練をこなしている。実は一番多忙だったのが彼女だ」
「いつの間に・・・ってそれよりどうやってここまで?」
『あら寺川さん、あたしもピブリダーのパイロットだもの。大利根さんの船まで増槽つけて航続距離ぎりぎりだったわ』
『隊長! 俺やることないじゃないか!』
「何を言う。針の穴を貫くパッティングの腕前に期待しているぞ」
クラブ「J」のマダムとプロゴルファーというコンビネーションは、それらが仮の姿としても異色であった。しかしめぐみとマリはピブリダーの専任パイロットでもあり、操縦技術は天田よりも優れている。
『ここ一番は一平さんの出番になるわよ。それまではおねーさんに任せなさい』
『ちぇっ!』
ブリッジが一斉に笑い出したところで天井が動き出した。偽装パネルも相当の面積と重量があり展開に時間がかかる。トーマスが服部六助に機関の準備を要請する。
「ミスター・ハットリ、メインエンジンアイドリング。補助スラスターアイドリング。アストランダ―ロケットは点火待機」
「SМJ! ロクさんでいいぞ」
ごとん、という響きと共にシートが傾き始めた。いや、ブリッジ全体が傾いている。МT号の船底が開いて架台後部が海中に落ち込み出したようだ。設計通りであればMJ号のノズルと翼端はぎりぎり甲板上で80度の仰角をとることになる。
「仰角50。天候は薄曇り。風、微風」
「各員シートベルトを確認」
「仰角70。観測範囲に一般艦船、敵反応なし」
「艦尾甲板上で安定。両翼展開!」
「仰角、80になります!」
「ロクさん、補助スラスター点火!」
「待ってました! 両翼推力全開」
「各員衝撃に備えよ、行くぞ宇宙へ!」
補助推進はゆっくりとMJ号の巨体を架台にこすりつけながら浮き上がらせる。翼端から噴射される光が波を蹴立て、固定アームの関節点を稼働させて呼応するMT号の僅かな前進も手伝い、空中に浮遊した。
「ロクさん、スラスターをオーバーブーストへ!」
「はいよっ」
MJ号の高度が徐々に上がり、MT号の艦橋をかすめていく。
「高度、海面から400m」
「アストランダ―ロケット、点火!」
数秒と違わずブリッジがどんっと揺さぶられ、同時に体がシートバックに押し付けられさらにめり込んでいく。
「リフト・オフ成功! あー、舌を噛みそうっ」
フル加速の開始によって体感する荷重も三倍、五倍となる。MT号の巨体は地球の自転に依存しながら、重力を振り切り秒速8キロへと速度を上げていく。やがて加速は7Gに達した。
「衛星・・・兵器からの攻撃! MT号にっ」
マリが苦しそうに叫ぶ。当も思わず上体を起こそうとするが動きが取れない。
「こっちを狙ったが・・・速度差で外したか!」
「MT号に命中シマ・・・」
噴射炎と排気の帯をたなびき上昇するMJ号には成す術がなかった。
※本作は勝手に書いているオリジナルです。同作関係者などとの関係はありません
ようやく飛んだよ。