春に久々のLIVEだー!と言って、 新月サンが二階でドラムの練習始めたら・・・ 天井から響いてくる〝異音〟にビビる猫ず(笑) (練習用のキットだから本当に打音だけ) でんいちは・・・聞いた事あるはずだけどな。 ちなみに。 ここに写っていないでん助は、我関せずで ひとりボリボリとご飯食べてました。
「ほぼ」週刊エスクードを作る 05
 二次塗装を行った本体の乾燥は済みました。試しにマスキングを剥がしてみました。自動車用マスキングテープの糊の強さは半端なものではなく、やはりハイストーリーの元の薄い塗装に悪さをしていました。糊自体が固着してしまったり塗装を剥がしてしまったりで、ツートンカラーの腰下の金系は見られたものではありません。凸凹を削り取り磨き直して再塗装するための作業を、例によって雑に行っているところです。青系の塗装は何度か吹き直しをやりました。
二次塗装を行った本体の乾燥は済みました。試しにマスキングを剥がしてみました。自動車用マスキングテープの糊の強さは半端なものではなく、やはりハイストーリーの元の薄い塗装に悪さをしていました。糊自体が固着してしまったり塗装を剥がしてしまったりで、ツートンカラーの腰下の金系は見られたものではありません。凸凹を削り取り磨き直して再塗装するための作業を、例によって雑に行っているところです。青系の塗装は何度か吹き直しをやりました。
ここから先の塗装は面積的に吹き付けが面倒。というよりマスキングが億劫。細かな部分の修正塗装や上塗りもあるため、こんなこともあろうかのガンダムマーカー採用です。なぜかというと、例えばフロントフェンダーのウインカーレンズなんてたったの二か所で2ミリ程度です。ミニボトルのクリアオレンジを通販で買おうとしたら、単価はまあまあだけれど注文は3個からとかぬかしやがるのです。たぶん1滴か2滴の必要量に、そんなもん買えるかと憤慨してのことです。
ガンダム系のプラモデルなんて、それこそ最後に作ったのはいつのことか覚えていないくらい過去の話。ガンダムマーカーの存在は知っていたし別の小物塗装に使ってもいましたが、それらはガンダム用とか量産型ザク用程度のいわゆるアニメ版オリジンカラーでしかありませんでした。最近のは銀系から黒鉄色までどころか、金系、オレンジ系などすべてメタリック塗装の出来るセットがあります。これでツートン部分もグリルも背中のスコップも、もちろんフェンダーマーカーも塗り分けられる。
しかしソリッドの赤や黒、白といったものはオリジンカラーを選ぶしかなく、手持ちのガンダムマーカーも中身が固着してきて塗りにくいので新調することにしました。残る問題は、ローガンズとなった自分の視力と、指先の震えです。この作業と同時に、タミヤのミリタリーSASジープからスコップとホルダーに使えそうな部品を切り取り、スペアタイヤへの接着を開始します。ルーフレールは華奢すぎるので最後の工程に回します。
そろそろお役御免・・・と言えない愛着
 一番太っていた(今でも太いですよ)頃に買ったエドウィンもこの有様です。当時に比べれば程度問題程度にウエストの数字は小さくなっているので、こいつはベルトをさしてもずり落ちてしまうし、厚着をしてそれらを詰め物にしないと履けないくらいでかいサイズ。夏になったらひざ下を切り飛ばして半ズボンに・・・しようがないのです。新しいのを買えば済むことなんですが、これはこれで、寒いけど捨てられないから僕は断捨離下手な男なのです。
一番太っていた(今でも太いですよ)頃に買ったエドウィンもこの有様です。当時に比べれば程度問題程度にウエストの数字は小さくなっているので、こいつはベルトをさしてもずり落ちてしまうし、厚着をしてそれらを詰め物にしないと履けないくらいでかいサイズ。夏になったらひざ下を切り飛ばして半ズボンに・・・しようがないのです。新しいのを買えば済むことなんですが、これはこれで、寒いけど捨てられないから僕は断捨離下手な男なのです。
この膝、二年前にも扱っているんですが、だいぶ裂けましたねー。
飲み切れるンでしょうか・・・
夜中に突然いなりずしが食べたくなったりする初午です
 なんか突然ふるーいCМのフレーズが湧いてしまいました。そのせいでは決して無い、初午です。ざっと1300年ちょっと前の2月最初の午の日、穀物の神が伊奈利山に降臨したという起源から、京都の伏見稲荷を頂点に、全国各地の稲荷神社が豊作やら商売繁盛やら家内安全やらの開運祈願を繰り広げます。五穀豊穣の神が稲荷神ということとなり、その使いが狐であるというのはもう「基本設定」なので揺るがない話ですが、油揚げが狐の好物だという部分は「それほんと?」とも思います。
なんか突然ふるーいCМのフレーズが湧いてしまいました。そのせいでは決して無い、初午です。ざっと1300年ちょっと前の2月最初の午の日、穀物の神が伊奈利山に降臨したという起源から、京都の伏見稲荷を頂点に、全国各地の稲荷神社が豊作やら商売繁盛やら家内安全やらの開運祈願を繰り広げます。五穀豊穣の神が稲荷神ということとなり、その使いが狐であるというのはもう「基本設定」なので揺るがない話ですが、油揚げが狐の好物だという部分は「それほんと?」とも思います。
稲荷寿司が「おいなりさん」とも呼ばれる所以もここにあり、油揚げにご飯を入れて産み出されていったと出自も諸説あるわけですが、雑食肉食とはいえ狐がそれを好んで食うのか?と勉強したらば、稲作の世界で害獣除けのために稲荷神に奉納していた初期の供物はネズミなどの小動物だったと。後に仏教が絡んできて殺生しちゃならんという影響を民が受け入れ、豆腐や大豆から油揚げが作られ供物に取って代わった歴史が見えてきました。
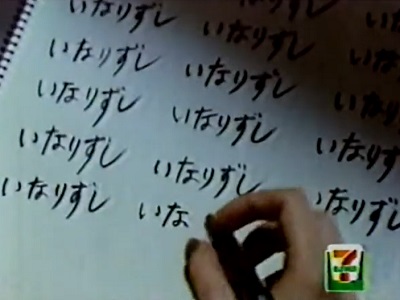 いやはや仏教の介入が無かったら、夜中に突然あんなのを食いたくなる文化のままだったかもしれない。稲荷寿司で良かったですよ。
いやはや仏教の介入が無かったら、夜中に突然あんなのを食いたくなる文化のままだったかもしれない。稲荷寿司で良かったですよ。
そんなわけで本日が初午の日なんですが神がかった話をすると、穀物の神が降臨したといわれる和銅4年は、西暦にすると711年でした。突然降ってわいた、表題に使ったフレーズをもともとCМで使ったのは、あの「セブンイレブン」なのです。
お願い、ぐーぐる先生!
はるちゃんが「箱で貰っちゃって飲みきれないから」
と、分けてくれたお茶。
〝菊花茶〟って書いてあるので、菊の花乾燥させた
漢方茶だと思っていたら、陳皮とかクコの実とか
色々入った紅茶だった・・・
1回目は2分・2回目は3分・3回目は5分浸せ
って書いてあるのかなーとは思ったけど
本当に合ってるのか?という疑問から
ぐーぐる翻訳起動。うん、だいたい合ってた。
試しに飲んでみたら、口に含んだ瞬間は漢方薬っぽくて
後味は紅茶。氷砂糖が入っているので、甘い。
漢方薬っぽくて甘いって時点で多分新月サンは飲まない
と、思うので。
・・・がんばって一人で飲むか・・・
商品名:八宝菊花茶
カテゴリー: フレーバーティーバッグ
原材料: 氷砂糖、紅茶、リュウガン、ナツメ、オレンジの皮、カシアの種、菊、クコの実
食品製造許可番号:SC11435062301947
製品規格番号: GH/T 1247
淹れ方:ティーバッグをカップに入れ、95〜100℃の沸騰したお湯を約200ml注ぎます。
1回目は2分、2回目は3分、3回目は5分浸してから飲んでください。
原産地: 福建省漳州市
賞味期限: 18か月
製造日: 箱の上部をご覧ください
どうせ呼ばれるだろう「ジムノマ」って
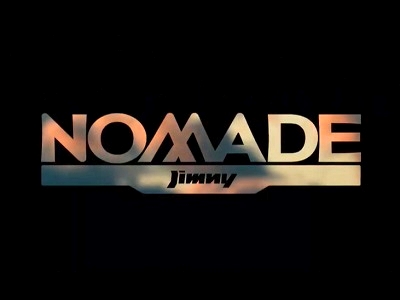 乗ってもいない車のことなんか書ける材料ありませんが、巷の声は「遂に」よりも「エスクードノマドを思い出す」方が多い感じがして、ジムニーノマドのサブネーム効果は抜群です。スズキは長年これを作り出したかった。ここまでTD01Wに寄せてくるとは、スズキとしも理想のパッケージのはず。ジムニーから生まれたものはジムニーに還るということに、僕なんかは悲喜こもごもなのです。いやまあ「喜」の部分はあんまりないんですけどね。
乗ってもいない車のことなんか書ける材料ありませんが、巷の声は「遂に」よりも「エスクードノマドを思い出す」方が多い感じがして、ジムニーノマドのサブネーム効果は抜群です。スズキは長年これを作り出したかった。ここまでTD01Wに寄せてくるとは、スズキとしも理想のパッケージのはず。ジムニーから生まれたものはジムニーに還るということに、僕なんかは悲喜こもごもなのです。いやまあ「喜」の部分はあんまりないんですけどね。
NOMADEという言葉は、スズキでは1990年に商標登録していて、エスクードのロングモデル登場時に初めて世に出ているわけですが、登録時の表音は「ノメード」で、ひょっとすると「ノマド」表音の別な登録商標と被ったのかもしれません。そのあたりは邪推に過ぎませんが、エスクードにノマドのサブネームが付いていたのは案外短く、TD51Wや61Wが出てきた96年には廃止されています(この記事は間違い)。しかし商標自体は更新されてきたことで、ジムニーに活用されることになった。まー昨今の言葉略し文化的には、あっという間に「ジムノマ」なんて呼び方をされるんでしょう。ついでだからその際シエラは「ジムシー」←あのキャラが浮かんでしまう。
茶化すのはここまでとして、珍しくも二階堂裕さんがジムノマよりもエスクードノマドを褒めています。命名者は鈴木俊宏社長だそうな。エスクードのフレーム車体廃止を止められなかったことへの後悔がジムニーノマドの原点ということだそうで、そこはリップサービスだと感じるんですが、ほんとに書くの?エスクードを絡めたJCJ本(少なくとも一年半後に出すプランらしい)。エスクード本については一回ウソつかれているし、この路外軌道帖記事に使っているエスクードもノマドじゃないしで、先行きあてにはなりません。
ところで各車の室内長×室内幅×室内高(mm)
ジムノマ
1910×1275×1200
シエラ
1795×1300×1200
ハスラー
初代
2160×1295×1250mm
二代目
2215×1330×1270mm
エスクード(初代1600)
TA01W 1595×1275×1240mm
TD01W 1680×1310×1280mm
 この数字をどう見るかは手にする人それぞれの印象と実感になると思いますが、エスクードのノマドの室内幅でも、二代目エスクに乗ると初代は「狭さ」を体感しました。ハスラーの二代目は数字だけならグランドエスクード並みです。室内高は210mmの最低地上高を確保しての相殺と思われます。世間では「4人乗ることはあまりない」という論評なので、そんなに窮屈さは感じないのかもしれません。しかしジムニーもいよいよ「都市型四駆」におさまっちゃうことを誰も言わない。
この数字をどう見るかは手にする人それぞれの印象と実感になると思いますが、エスクードのノマドの室内幅でも、二代目エスクに乗ると初代は「狭さ」を体感しました。ハスラーの二代目は数字だけならグランドエスクード並みです。室内高は210mmの最低地上高を確保しての相殺と思われます。世間では「4人乗ることはあまりない」という論評なので、そんなに窮屈さは感じないのかもしれません。しかしジムニーもいよいよ「都市型四駆」におさまっちゃうことを誰も言わない。
と思ったら注文受付停止とはみっともない・・・5万台のバックオーダーを読み違いするというのは、嬉しい悲鳴どころか能天気過ぎの経営です。しかしうがった見方をすると、こういうのって例のウイルス攻撃と似たり寄ったりで、スズキにとってはいい迷惑なんだろうなあ。口が裂けても迷惑とは言えないでしょうけど。
月遅れの新年会。
東風解凍なれど風は南から
 「東風解凍」、はるかぜこおりをとく七十二候7番目の季節が昨日から始まり、7日あたりまでに春めいた陽気の兆しがもたらされる頃となっています。我々はたいていの場合「四季」のうつろいは感じるものの、それを細分化して二十四節気、さらに3つに分けるのが七十二候と、古代中国の人々には我々以上に優れた体感センサーと風物を見極める目があったようです。春風が吹いて、水面を覆っていた厚い氷を解かし出す、わずか五日間の季節の感じ方です。
「東風解凍」、はるかぜこおりをとく七十二候7番目の季節が昨日から始まり、7日あたりまでに春めいた陽気の兆しがもたらされる頃となっています。我々はたいていの場合「四季」のうつろいは感じるものの、それを細分化して二十四節気、さらに3つに分けるのが七十二候と、古代中国の人々には我々以上に優れた体感センサーと風物を見極める目があったようです。春風が吹いて、水面を覆っていた厚い氷を解かし出す、わずか五日間の季節の感じ方です。
春風は「東風」のことで、「はるかぜ」とも「こち」とも呼ばせますが、我々の暮らす地理感覚だと暖かめの大気が風になって届くのは「南」からのような気がします。しかもまだ南岸低気圧が渡って来そうな天気図と馬鹿みたいな寒さも続いているしで、95万キロに達したたクルマの暖気はトルクコンバータ内の固着を解くために長めにしなくてはなりません。
昨日の話だけで閉じるわけにもいきませんから、やっぱり古代中国の天文側の暦のことで、2月4日を紐解きます。これは北斗七星の運行をもとにした「十二直」(じゅうにちょく)というもので、北斗七星が北極星に対してどの位置にあるかを12等分して時間や日・季節を表すために作られました。
この12の意味には建(たつ)、除(のぞく)、満(みつ)、平(たいら)、定(さだん)、執(とる)、破(やぶる)、危(あやぶ)、成(なる)、納(おさん)、開(ひらく)、閉(とづ)が与えられており、星の位置関係で巡っていきます。今日、2月4日はこのなかの「満」にあたり、物事が満ちあふれ、婚礼・旅行・引っ越しなどほぼ何をやっても吉といわれています。ただし同じ古代中国の「二十八宿」(にじゅうはっしゅく)という天文学の示すところによると、今日は「翼宿」(よくしゅく)と言い、種まきや旅行は吉ですが、婚礼については真逆の凶を説いています。
とりあえず旅行は吉らしいので、どこか知らない街へ立ち寄ってみます。旅行じゃなくて仕事だけどね。




