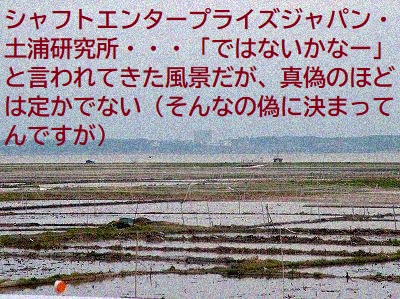「TVシリーズから『劇場版2』にフォーカスした展示会が、グリフォンの聖地・土浦で遂に開催!」
「TVシリーズから『劇場版2』にフォーカスした展示会が、グリフォンの聖地・土浦で遂に開催!」
なななな、なんという外連味にあふれた文言であることか!
というパトレイバー展が来月の13日まで、土浦駅西口横の市民ギャラリーで開かれておりまして。
 すごいですよねえ。「グリフォンの聖地」って言い切っちゃった主催者は他ならぬ土浦市です。「機動警察パトレイバー」をご存じの方ならば、アニメ、コミカライズ版ともに頻繁に「シャフトエンタープライズジャパン土浦研究所」が登場するので、「おー」と膝を叩いてくれることでしょう。フロアの最初のコーナーは、土浦研究所謹製のグリフォンとシャフトの面々の展示しかありません。展示画は撮影できませんが、センターにあるグリフォン立像は写せます。
すごいですよねえ。「グリフォンの聖地」って言い切っちゃった主催者は他ならぬ土浦市です。「機動警察パトレイバー」をご存じの方ならば、アニメ、コミカライズ版ともに頻繁に「シャフトエンタープライズジャパン土浦研究所」が登場するので、「おー」と膝を叩いてくれることでしょう。フロアの最初のコーナーは、土浦研究所謹製のグリフォンとシャフトの面々の展示しかありません。展示画は撮影できませんが、センターにあるグリフォン立像は写せます。
 展示目録が無かったことは無念でしたが、グリフォンから一歩引きながらも、特車2課の装備やイングラムの模型展示もあり、設定寸のリボルバーカノンももちろんある。上海亭の岡持ちもあれば、「あんなの」まである。一連の展示はヘッドギア側からのパッケージ貸与なのでしょうけれど、土浦以外だったら小笠原でないとグリフォン主体の企画にはなりません。いろいろと小芝居の効いた二大(よく見ると3台)レイバー土浦市役所前の激闘という葉書がもらえます。
展示目録が無かったことは無念でしたが、グリフォンから一歩引きながらも、特車2課の装備やイングラムの模型展示もあり、設定寸のリボルバーカノンももちろんある。上海亭の岡持ちもあれば、「あんなの」まである。一連の展示はヘッドギア側からのパッケージ貸与なのでしょうけれど、土浦以外だったら小笠原でないとグリフォン主体の企画にはなりません。いろいろと小芝居の効いた二大(よく見ると3台)レイバー土浦市役所前の激闘という葉書がもらえます。
 いやー地元(広義の解釈)でこんな充実した展示会が見られるとはありがたいことで、主催者である市役所の人に「面白かったです」と申し上げながら、よくぞこんなにマニアックな企画を通されましたね、マンガ読んでないと出てこない発想ですよと伝えたら、
いやー地元(広義の解釈)でこんな充実した展示会が見られるとはありがたいことで、主催者である市役所の人に「面白かったです」と申し上げながら、よくぞこんなにマニアックな企画を通されましたね、マンガ読んでないと出てこない発想ですよと伝えたら、
「ウィキペディアの『土浦市』の項に書いてありました。それで知りました」
なぜ土浦なのかという原典はもちろんマンガや映像によるものとして正しいことですが、当然ながら三十代や二十代くらいの人だと、土浦研究所がどこにあるのかという裏話的なことまでは知らないよねえ。