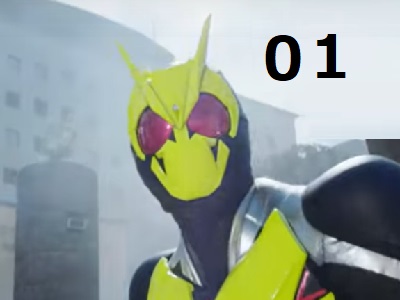ん? 一人・・・
「スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」が公開となります。ジョージ・ルーカスが70年代後半、少年時代からスペースオペラの9つのエピソードを温めながら、そのうちの4番目の物語を世に送り出し、とうとう最終章までやってきました。
78年にそのエピソードⅣを観たとき、こうなるとは思ってもいなかったですよ。40年以上かけてひとつの舞台を完結させるほど、壮大というか呑気というか。関係ないですが小松左京さんは存命中、「さよならジュピター」原作小説内で「スター・ウォーズ30」という言葉を綴っていましたけど。
それでふと思ったのです。
今まで、資金と物量で作られてきたスター・ウォーズのシリーズも、圧縮して物語をまとめると、9本も要るかこの映画? と言えなくもない(いやいや、要るんですよ実際には)。40年以上かかったのは、エピソードⅣの時代では、ルーカス氏自身が技術と予算の問題で一気に描けなかったという事情があってのことですが、それらのハードルをクリアしながらエピソードⅨに至る。これだけ時間と資金と技術を投じていけば、そりゃシリーズも膨らみますよ。
この比較対象で、真逆のポジションに置き続けてきた、東映の「宇宙からのメッセージ」を思い出すと、逃げようがないほどそれなりのものしかできない。讃えたいところが一つもない東宝の「惑星大戦争」よりはマシとはいえ、ほんとに総論としてはとほほな映画だったのです。と、今まで言ってきました。でも、ほんとにそうなのか?と、ふと考えが揺らいだのです。
洋画がヒットしたら似たような路線を速攻で作って当てに行く。という東映路線にのっかって作られた「宇宙からのメッセージ」は、観ようによってはスター・ウォーズが9本もかけて描いたスペースオペラを、たった1作でやってのけている。これは光子帆船プレアスターの美しさと、楽曲の中のエメラリーダのテーマのすばらしさに次ぐ評価軸だったのです。ストーリーを日本の冒険活劇の古典(南総里見八犬伝)に求めたとはいえ・・・、否、欧米のいかにもな神話なんぞに頼っていない時点で、東映流短期間でまとめた企画として、企画力はたいしたものだったんだよと、今更ですが気が付きました。
松竹にやらせたら「男はつらいよ」のシリーズなんか30年かけずに49本できちゃってるんですもん(50本目はこの27日に封切り)。まあそれを言ったら洋画の世界にもスーパーマンやバットマンやスタートレックがあって、ターミネーターがにじり寄っているとも言えるのですが。それらに仮面ライダーとスーパー戦隊をぶつけるのはまた別の話ですからやめときましょう。
ヒロインだってさー(それでそこかよ)、キャリー・フィッシャー、ナタリー・ポートマン、ディジー・リドリーと比べたって、志穂美悦子さんまったく引けをとらないじゃないですか(すいません、僕はパドメ・アミダラ役のナタリー・ポートマンが一番だと思ってます)。
 なぜこれほど不細工なプロポーションで、つるんとした装甲がかっこいいと思えたのかは謎だったんですが、おそらくそれはプロレスラー然としたブルマーのような腰部のマジンガーZが嫌だったんだと思います。ならば全身真っ赤の機体の方が、機械っぽい。のちに制作されるマッハバロンの方が絶対にスマートかつごっついのに、どうしたことかレッドバロンのこの造形は、結果としての潔さで贔屓せずにはいられないのです。
なぜこれほど不細工なプロポーションで、つるんとした装甲がかっこいいと思えたのかは謎だったんですが、おそらくそれはプロレスラー然としたブルマーのような腰部のマジンガーZが嫌だったんだと思います。ならば全身真っ赤の機体の方が、機械っぽい。のちに制作されるマッハバロンの方が絶対にスマートかつごっついのに、どうしたことかレッドバロンのこの造形は、結果としての潔さで贔屓せずにはいられないのです。 当時、指紋認証と声紋認証を強奪防止セキュリティに導入したことは新しかった(まあ突破されちゃうんですが)し、操縦桿をどう使うのかが理解できなかったけれど、「ファイトレバー」を入れるだけでどうやら基本動作の格闘戦は可能だという描写や、操縦室が灼熱化したら百円入れてクーラーが機能する(笑)スポンサーCМも楽しかった。つまるところ、設定をとことん練りこんでも、押し付けてこない適当さって、案外大事だったと感じさせるのです。
当時、指紋認証と声紋認証を強奪防止セキュリティに導入したことは新しかった(まあ突破されちゃうんですが)し、操縦桿をどう使うのかが理解できなかったけれど、「ファイトレバー」を入れるだけでどうやら基本動作の格闘戦は可能だという描写や、操縦室が灼熱化したら百円入れてクーラーが機能する(笑)スポンサーCМも楽しかった。つまるところ、設定をとことん練りこんでも、押し付けてこない適当さって、案外大事だったと感じさせるのです。 途中のつなぎの話数はぐだぐだモノなんだけれど、根幹はテクノロジーを介する人類の未来の行方という、がっちりとした路線の子供向け番組。残念ながら特撮巨大ロボットものはアニメーションのそれに比べて数少ない。それでも、やっぱり、トランスフォーマーじゃダメなんですよ。46年前にこれだけやっている。ついでに「哀 戦士」より8年も早く井上忠夫(大輔)で主題歌作曲してます。と、これだけ理屈つけてソフトを買ったというオチ・・・
途中のつなぎの話数はぐだぐだモノなんだけれど、根幹はテクノロジーを介する人類の未来の行方という、がっちりとした路線の子供向け番組。残念ながら特撮巨大ロボットものはアニメーションのそれに比べて数少ない。それでも、やっぱり、トランスフォーマーじゃダメなんですよ。46年前にこれだけやっている。ついでに「哀 戦士」より8年も早く井上忠夫(大輔)で主題歌作曲してます。と、これだけ理屈つけてソフトを買ったというオチ・・・