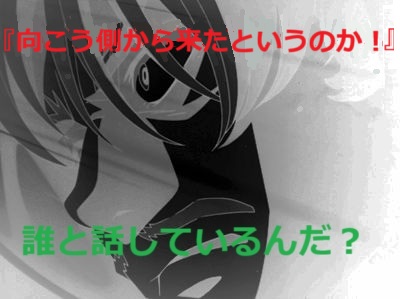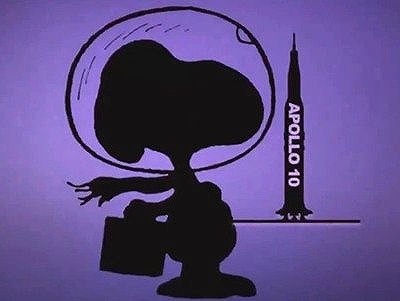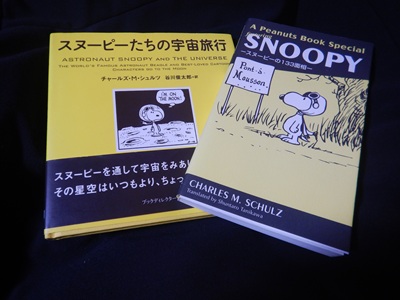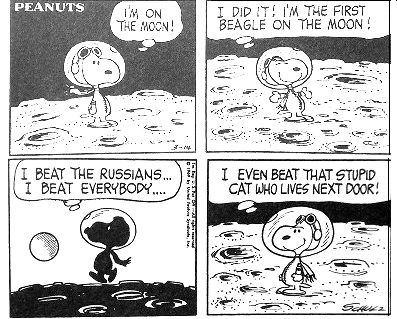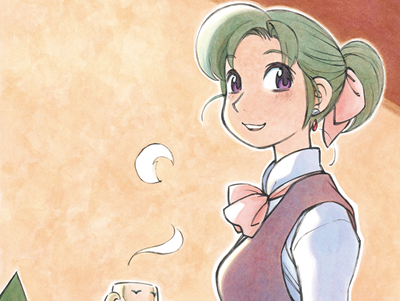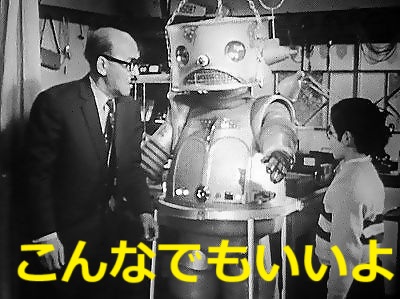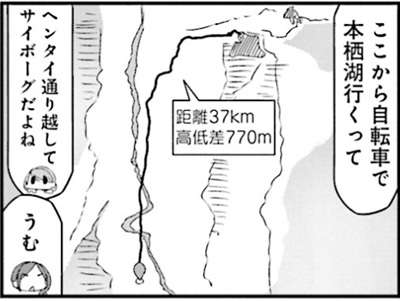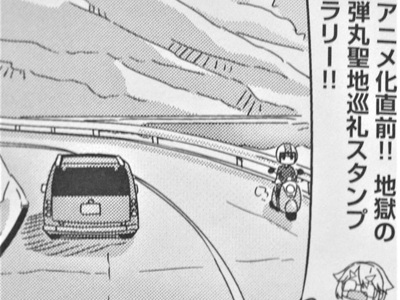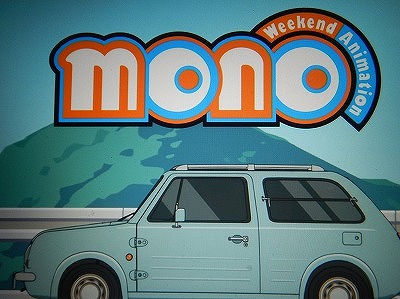ハサミ、マスキングテープ、付箋、クリアファイル、ジップロックパッケージ、ホチキスと・・・入れ物そのもの(下の写真)
ハサミ、マスキングテープ、付箋、クリアファイル、ジップロックパッケージ、ホチキスと・・・入れ物そのもの(下の写真)
ペヤングソース焼きそばが誕生50周年なんだそうです。そこに着目した宝島社がまるか食品と共同開発。ムックの付録についておりました。入れ物なんか昔ながらの蓋付き仕様(スチール製)です。
 まるか食品でも50周年記念で味付けバリエーションを展開するようですが、メガ盛りパッケージなどで話題をさらってきたペヤングは、この付録ではレギュラーサイズの半分くらいのコンパクトさで、カバンに入れてもかさばらない大きさ。クリアファイルとジップロックをどう使いこなすかはユーザー次第です。
まるか食品でも50周年記念で味付けバリエーションを展開するようですが、メガ盛りパッケージなどで話題をさらってきたペヤングは、この付録ではレギュラーサイズの半分くらいのコンパクトさで、カバンに入れてもかさばらない大きさ。クリアファイルとジップロックをどう使いこなすかはユーザー次第です。
まあ使いであるけれどこれ、使うのもったいない(笑)
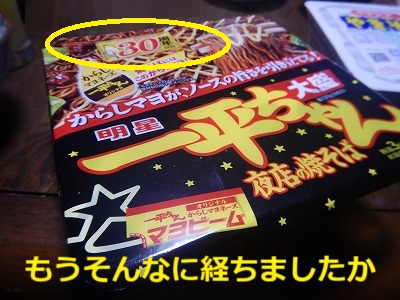 そばを焼く、という調理方法を根底から変えてしまった、厳密には焼きそばではないインスタント麺が、現代において残している改良点は「湯切り」による熱湯の処分でしょうか。それさえもどこだったかのメーカーは「それでスープを作って」とスープ用粉末もつけていたと思います。各社しのぎを削ってます。ペヤングに続いて明星一平ちゃんも30周年、こちらはからしマヨネーズという切り口が我が家に受けていて、シェアの奪い合いが続いています。
そばを焼く、という調理方法を根底から変えてしまった、厳密には焼きそばではないインスタント麺が、現代において残している改良点は「湯切り」による熱湯の処分でしょうか。それさえもどこだったかのメーカーは「それでスープを作って」とスープ用粉末もつけていたと思います。各社しのぎを削ってます。ペヤングに続いて明星一平ちゃんも30周年、こちらはからしマヨネーズという切り口が我が家に受けていて、シェアの奪い合いが続いています。