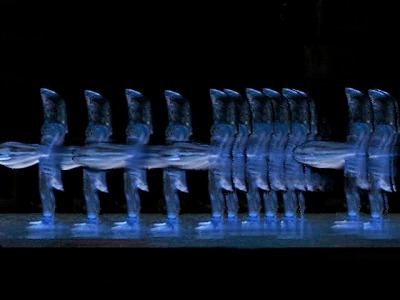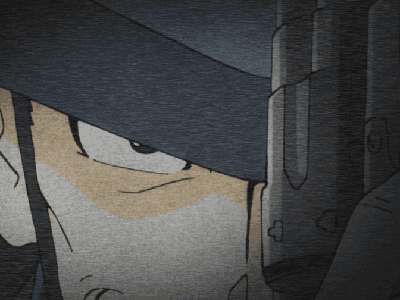「おかえりモネ」が本日の放送で大団円となります。二転三転の急展開ではなく、割と短い時間軸の中でじれったいほどゆっくりと丁寧に、主人公の人生を描いた良作だと思います。高卒後(一部で中卒時も)から現在までの数年間の変化を、主人公自身が驚くほどいでたちも表情も大人になっている(設定上、霰と同い年)のが印象的です。清原果耶はまだ19歳。「あさが来た」「透明なゆりかご」「なつぞら」といい仕事をしています。
「おかえりモネ」が本日の放送で大団円となります。二転三転の急展開ではなく、割と短い時間軸の中でじれったいほどゆっくりと丁寧に、主人公の人生を描いた良作だと思います。高卒後(一部で中卒時も)から現在までの数年間の変化を、主人公自身が驚くほどいでたちも表情も大人になっている(設定上、霰と同い年)のが印象的です。清原果耶はまだ19歳。「あさが来た」「透明なゆりかご」「なつぞら」といい仕事をしています。
気仙沼の離島を故郷とする主人公は、東日本大震災の日、たまたま高校受験の合皮発表を見に行き仙台で被災したため、島における津波被害や被災者の修羅場に居合わせませんでした。家族や友人たちに対するどことない後ろめたさが、郷土で誰かの役に立ちたいという思いに変っていき、気象予報士の道を選び、お天気お姉さんに抜擢されながらも島に帰ってきます。ゆっくりやってる割にはこのあたりの、予報士としての仕事場面が少なかったとも感じますが、朝ドラヒロイン随一の地味なキャラクターでありながら、存在感があります。
その日、地元にいなくて葛藤の日々を送った彼女・百音に対して、あの頃の僕は、「気仙沼に『大島』があるのかよ」くらい余所者になり立てで被災していました。仙台在住の前任者から引き継がれたのはただ一言「東北人は寡黙で腹の内を明かさない」(失礼なようだけど、本当にそう言われた)。まあ僕なんか行き当たりばったりの男ですから「そんなこと言われたって俺は俺でしかないよ」と返事をしたものの、マジかよとも思いながらの仙台赴任。あいさつ回りを終えたら震災という、百音と真逆の経験でした。
ドラマを見ながら、全く反対の立場を過ごしてきた彼女と自分に唯一、共通するものがあるなあと感じたのは、周囲が与えてくる先入観の種。それにどうやって向き合うのかが、それぞれの軸足として大事でした。同業者は僕のいないところで「しょせん腰掛の外人部隊」だと揶揄していたそうですが、二年で転勤していく国の役人とは違いましたから、居られるだけ居ようとせせら笑って揶揄など無視していたらば、東北のあちこちの人々は「そうか、お前はあのときここ(東北)にいたんだな」と、揶揄自体が逆効果になるような変化をいただくことになりました。
 写真は被災一年後の気仙沼。百音の住む島は右端に位置し、今は架橋されていますが、当時は橋の袂の工事現場まで行くのに「冗談じゃねーよ」という時間を要しました。今だったら仙台から二時間で行けちゃうはず。でも、いち早く復興した街の一つだけれど、これから十年、二十年後、地元の後継者が元気で居続けてくれないと、世の中自体が先細る中、街の未来も変わってしまいます。百音と幼馴染の若者たちは、家族や地域の人々の軸足を担うことになります。
写真は被災一年後の気仙沼。百音の住む島は右端に位置し、今は架橋されていますが、当時は橋の袂の工事現場まで行くのに「冗談じゃねーよ」という時間を要しました。今だったら仙台から二時間で行けちゃうはず。でも、いち早く復興した街の一つだけれど、これから十年、二十年後、地元の後継者が元気で居続けてくれないと、世の中自体が先細る中、街の未来も変わってしまいます。百音と幼馴染の若者たちは、家族や地域の人々の軸足を担うことになります。
 帝国宇宙軍付属沖縄女子宇宙高等学校三年生の才色兼備の優等生、アマノカズミは、2004年11月15日生まれ。本日が申年にしてB型で蠍座の17歳にあたる誕生日なのですが、事の発端である2015年の白鳥座宙域戦闘で遭難・漂流してきた第三世代型宇宙戦艦るくしおんの捕捉確認亜光速ミッションに12秒の乱れが生じ、上官、同僚とともに地球帰還が半年遅れてしまったため、今頃はまだ太陽系のどこかにいるはずです。
帝国宇宙軍付属沖縄女子宇宙高等学校三年生の才色兼備の優等生、アマノカズミは、2004年11月15日生まれ。本日が申年にしてB型で蠍座の17歳にあたる誕生日なのですが、事の発端である2015年の白鳥座宙域戦闘で遭難・漂流してきた第三世代型宇宙戦艦るくしおんの捕捉確認亜光速ミッションに12秒の乱れが生じ、上官、同僚とともに地球帰還が半年遅れてしまったため、今頃はまだ太陽系のどこかにいるはずです。 この世界では、地球人類は外宇宙に進出する科学文明を有しながらも、それを銀河系レベルでは宇宙のがん細胞発症とみなされ、正体不明の宇宙生物群に襲われています。2021年以降は宇宙が白くなるほどの敵の襲来で、太陽系外延部はえらいことになっているのです。いや本当なら主人公タカヤノリコの誕生日である9月12日に書いておくべき話だったんですが、すっかり忘れてましたよ「トップをねらえ!」。昭和の終わりの作品だものなあ。
この世界では、地球人類は外宇宙に進出する科学文明を有しながらも、それを銀河系レベルでは宇宙のがん細胞発症とみなされ、正体不明の宇宙生物群に襲われています。2021年以降は宇宙が白くなるほどの敵の襲来で、太陽系外延部はえらいことになっているのです。いや本当なら主人公タカヤノリコの誕生日である9月12日に書いておくべき話だったんですが、すっかり忘れてましたよ「トップをねらえ!」。昭和の終わりの作品だものなあ。