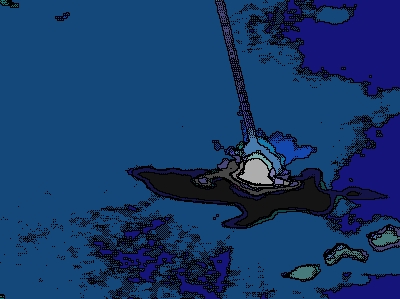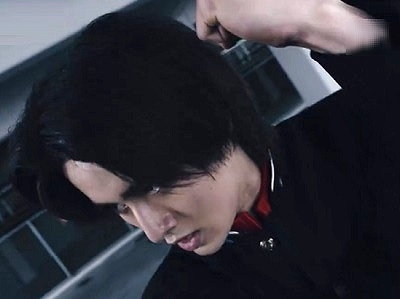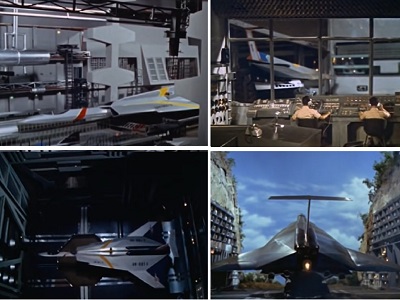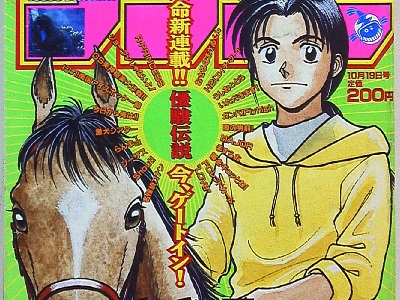東京・中野の駅前は21世紀半ばに大変貌を遂げた。
東京・中野の駅前は21世紀半ばに大変貌を遂げた。
皇居と霞が関を中心とした都心三区から西に外れたエリアには、20世紀の高度経済成長期以降長らく都心への通勤居住ゾーンとしての位置づけがなされていたが、東京湾にほど近い都心には巨大災害に対する脆弱さもまた語り継がれるなかで、都心から副都心の関係とは別の補完機能が求められてきた。中野駅周辺は、その副都心の一つではあったが、どちらかといえば都民生活や文化面での持ち上げ方が強い。
中野の街はおよそ東京、さらには国際社会の日本というポジションとなる政治経済とは無縁の街だった。そこへきて都心再開発、臨海副都心開発も行きつくところまで進み、西側のタネ地が有望視されている。
一部屋四億円など途方もない付加価値が生み出されるタワーマンションの誕生は、およそ中野の街らしさとは乖離しすぎだと揶揄されたが、巨大災害時に都心に建つ個々の高層建築が倒壊を免れたとしても、ゾーンとして見た場合の危機回避には、そこへ近づけないのでは防災対策も意味がない。
矢吹コンツェルンはいち早く都心からの拠点移築を果たし、中野駅前の再開発ビルに本部となる矢吹産業を据え、さらに西の立川市に共立銀行本店を移転させた。
矢吹産業は一見、都心からの脱落を演じて見せたように思えるがそうではない。立川の共立、八王子の双葉重工という一直線の矢吹コンツェルン主幹企業の東京護衛ラインを成立させ、その最前線に企業グループ総帥たる矢吹郷之助が指揮所を構えた形となっていた。
1940年代の敗戦時、海軍将校であった矢吹は諜報活動の経歴を理由にGHQから戦犯扱いを受けたものの、彼自身の商才を見抜いた米国占領軍は逆に矢吹を登用し、矢吹自身も昭和以降の世の中において危惧するひとつの危機感に対抗する手段を得るため、あえてこの契約に乗る形でアメリカを逆手に取ることとした。
矢吹は横田や横須賀とのパイプを作りながらGHQの要求する経済復興に奔走し、巨大な闇屋の親父となって、かつての部下を様々な業種業態の経営者として産業界に腰を据えたのである。
当然、米国の尖兵、手のひら返しと多方面から罵られることは避けられなかったが、東京復興は敗戦からわずか20年で形が整い、一部には「あの渋沢が蘇ったようだ」という評価も聞かれた。
そのような激動の敗戦処理の日々、矢吹は、新井薬師近くの借家に身を寄せていたが、将校として過ごした東中野時代を懐かしむよりも、この借家の暮らしが愛おしかった。終戦まで東中野に家はあったが、そこに帰ることはほとんどなかったのだ。
名うての海軍情報将校という経歴は、高齢となった矢吹を支える緑川登にとって、羨望の的であった。しかし緑川は矢吹の心中に宿る中野の街の逸話までは知らなかった。ましてや矢吹の実年齢を知ったらとても信じられない彼の佇まいや仕草、明晰な頭脳と言動には驚嘆するしかなかった。心臓にペースメーカーを入れていると聞いたことがあるが、GHQに逮捕されたときが二十代半ばだったはずだ。足腰だけでも超人的な若さである。叩けば埃も出ることだろうが、戦後四半世紀をかけ世界的規模のコンツェルンを立ち上げ、その多岐にわたる事業の陰で世界危機に対峙する民間組織をも生み出す野心とも愛国心ともつかない「こころざし」を、緑川は矢吹の背中越しにいつも感じるのであった。
「それで、Ozean Schwerindustrieの核融合炉が双葉の技術とは無縁だという証明は出来たかね」
「はい。この半年間、影に日向に調べてきましたが、あれは20年前の双葉の技術にすら辿り着いていません。実用には耐えられそうですが」
緑川の答えに、同席していた弓田エマが首をかしげた。
「そんなに時代差のある核融合炉が商用になるものなの?」
「なると思うよ、欧州でなら」
「それはやはり電力需給のひっ迫からかね」
「表向きはその通りだと思いますが、『融発』という発電所パッケージを量産する裏で、大型船舶発動機用としていくつかのサンプルを作りたかったと。そんな裏事情が聞こえてきました」
「船舶のエンジンに核融合炉・・・あまり乗りたいとは思わないわね」
エマの言葉に、緑川は苦笑する。
「客船ではなく、タンカーや大型貨物船のシェア争いを狙ってのことだよ。あとは軍艦」
「EUの総意ということではなさそうだね。NATOにも目立った動きはないが」
矢吹はそう呟きながら、ヨーロッパで不意に湧いて出た核融合炉の技術成果と成果品の商用化なるニュースに、Qの影を感じ取っていた。
「会長の読み通り、欧州では『シャルル・ドゴール』に次ぐ空母の原子力化構想を持つところがあって、そこに核分裂ではなく核融合を売り込んでいる動きが、Ozean Schwerindustrieにあるようです」
「しかしそれも表向きだということだね?」
緑川は腕組みしていた両腕を両膝にあてがい身を乗り出して言った。
「商用化対象の核融合エンジンは、常識で考えれば契約と発注によって建造にゴーサインが出るものでしょう? ところが既に2基、ラインアウトして、何処かに持ち出されているんです」
「いつの話かね」
「遡れるのは2年ほど前までです。もっともエンジン自体を目にした第三者はいないでしょう。私もつてをたどりながら伝票操作の痕跡を掴んで、これを精査すると核分裂型ではないと」
「Qの仕業なのかしら」
エマが再び首を傾げ、緑川に問いかける。
「あの・・・問題の核融合炉と、双葉重工の炉とではどこに性能差があるんでしょうか」
「それはねえ」
緑川は矢吹への視線をエマに移して答える。
「僕は専門家じゃないから細かいことはわからないよ」
「えー? だって20年は差があるってさっき・・・」
矢吹が笑いながら緑川の話を引き継いだ。
「Qがこれまで繰り出してきた潜水艦や空中戦艦は約10隻。そのすべてが核分裂をもとにした沸騰型原子炉搭載艦だ。原子炉の小型化高性能化、障害時の封鎖安全対策に関しては、残念ながら彼らの方が進んでいる。MJ号が撃沈、撃墜したにもかかわらず、目立った放射能汚染が見られなかったことが皮肉にもそれを証明している。まあその話は置くとして、米国の圧力に押されて我が国も戦後の原子力開発に拍車はかかったが、双葉にやらせてきたのは一貫して水素核融合技術だ。戦後78年を費やしプラズマ生成にこぎつけた」
「茨城の量子科学技術研究開発機構ですね」
「左様。フランスと共同開発中のITER計画に対する実証実験炉だが、コイルのトラブルが相次ぎ6年も遅れた。国際規模での発電向け運転は2050年代を目指しているが、それを実現させるためには高温プラズマを封じ込める磁場の安定が必須で、要となる超伝導コイルの品質確保が欠かせなかった」
「高温プラズマって、どれほどの高温ですの?」
エマの問いかけに緑川が答える。
「理論値ではね、1億度のプラズマを100秒間閉じ込めるのが現在の計画」
「太陽の・・・どころじゃありませんのね」
「お笑い草な話だか、実験炉のための実証実験炉を確実なものとするために、先行試験炉が必要だったのだ。JT-60SAはJT-60という初期型試験設備の後継機で、これの建造時に超伝導コイルの開発を任された企業のひとつが双葉だ。そこを突破口にトカマク型の核融合炉の超小型化も研究項目として加えてもらった」
「そうか。JT-60SAのサイズを公式資料で見たら、地上据え付け以外では大型艦船にしか積めないと思っていたんですが、その超小型核融合炉というのは・・・」
緑川が腑に落ちたような顔をする。矢吹は声を潜めて言った。
「太陽光プラズマエンジンというのはよくよく考えると訳のわからん名称だろう?」
「えっ? あれが実証実験のそのまた先行試験機ですの?」
「双葉が建造に成功するまで9基の試験機を経たものだよ。MJ号には10番目の試験機が載せられている」
エマはとんでもない機密を軽々しく話してよいのかどうか戸惑った。矢吹の秘書を務める桂 めぐみの表情をちらりと伺う。めぐみは普段、銀座のクラブ「J」に常駐しているが、マイティジャックにおいては諜報部門のリーダーであり、エマや緑川の上司というポジションにいる。そのめぐみは意外にもにこやかな表情でその場の対話を聞いている。エマと視線が合うと、そのまなざしは「気にしなくていいわよ」と言っているようだ。
「国際法的には危ない代物ですね。核施設としての対非核三原則は・・・」
「だからこその核融合なのだ。被爆国を祖国とする我々には、原子力に対する拒絶感を打ち消すことは出来ぬ。MJ号の主エンジン換装が完了してほっとしている。あれこそがJT-60SAに確実なデータを提供できる」
「10番目の融合炉・・・そういえば会長、EUが中国筋の産業スパイ被害に遭ったと吹聴していて、当然彼の国はこれを真っ向から否定していますが、あちらさんの核融合炉の実用化がITER計画よりも早く商業炉に行きつくのではないかとか」
「エネルギービジネスのイニシアティブ合戦は国に任せておけばいい。むしろ大陸で安全な核融合発電が普及していけば二酸化炭素の削減にも良い傾向となろう。しかしその隙をつけ狙うのが科学時代の悪意だ」
「Qが各国を手玉に取って、今回の衛星兵器問題のような暗躍をするのは目に見えていますね。これをご存じですか?」
緑川がメモを取り出した。
手書きのボールペン文字で「elfter Schwarzerもしくはschwarzer elfter?」と綴られていた。
「なんですの? ドイツ語かしら」
「何を示すものかはわからない。この数カ月、時折、諜報筋の暗号伝聞に乗ってくるようになった」
メモを凝視していた矢吹は眼鏡を外して眉間を指で押さえた。
「何かご存じのようですね」
「これはQの挑戦状だよ。『黒の11番』。そうか、衛星兵器はおそらく陽動だ。MJ号の不在を狙ってくるぞ」
矢吹は眼鏡をかけ直し、当八郎に暗号通信を送るよう弓田に指示した。タブレットで通信機能を立ち上げたエマが大声で叫んだ。
「会長! マリさんから二分前の着信が。MJ号、衛星兵器から攻撃を受けていますっ」
矢吹と緑川は互いに顔を見合わせ、同時に立ち上がった。
※本作は勝手に書き始めたオリジナルです。同作関係者などとの関係はありません
なんかこれを全部映像で見せられたら飽きそうです。MJ号の現場がこの悠長な対話を聞いたら怒っちゃいますよね。
それにつけても矢吹郷之助さんを存命させるととんでもないお歳になってしまう。和邇さんによると「矢吹さんの生年は円谷英二さんの生まれた年」という設定があったそうです。1901年・・・それこそ凄いことになるのでこちらではもう少し若くしました。マイティジャックのメンバーは全員、現代設定に年齢をスライドさせております。