去年に引き続き、ごろごろと実が生った枇杷。 何個か枝葉のスレで抉れてしまったけど 無事に色づいたので新月サンが採ってくれました。 今宵のデザートだー❤
豊作♪
真似して作ってみた。
文明開化の食道楽
 1858年に日米修好通商条約が締結され、翌年の6月2日、横浜が開港したという史実に基づき、横浜では「この機会がカレーの上陸にもつながるから横浜カレー記念日」という食文化があるそうです。ご当地記念日ですからそれでいいと思いますが、当時の日本にはまだ「食肉禁止令」の名残があったはずで、上陸はしたけどかの地の外国人居留地から外に出るのはすぐ、ということではなかったでしょう(鶏肉や蛙肉などの切り抜け方はあったと思われます)
1858年に日米修好通商条約が締結され、翌年の6月2日、横浜が開港したという史実に基づき、横浜では「この機会がカレーの上陸にもつながるから横浜カレー記念日」という食文化があるそうです。ご当地記念日ですからそれでいいと思いますが、当時の日本にはまだ「食肉禁止令」の名残があったはずで、上陸はしたけどかの地の外国人居留地から外に出るのはすぐ、ということではなかったでしょう(鶏肉や蛙肉などの切り抜け方はあったと思われます)
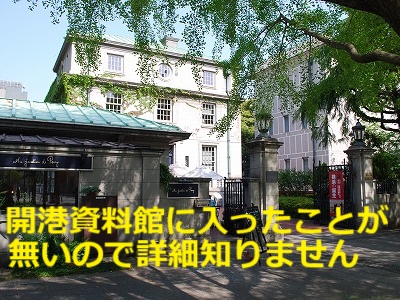 記録によれば、国内の書物にそれらしき記述が現れるのは1867(大政奉還の年ですね)年に西洋料理店主、三河屋久兵衛が幕府に提出した「西洋御料理御献立」、カレーの作り方が紹介された例は1872に出された「西洋料理指南」と、文明開化には横浜発ある程度の時間差が介在します。他方、長崎県では16世紀にキリシタン大名が派遣した天正遣欧使節が持ち帰ったとも伝えられているし、全国学校栄養士協議会が1982年、学校給食にちなんで、1月22日を「カレーの日」に制定してもいます。
記録によれば、国内の書物にそれらしき記述が現れるのは1867(大政奉還の年ですね)年に西洋料理店主、三河屋久兵衛が幕府に提出した「西洋御料理御献立」、カレーの作り方が紹介された例は1872に出された「西洋料理指南」と、文明開化には横浜発ある程度の時間差が介在します。他方、長崎県では16世紀にキリシタン大名が派遣した天正遣欧使節が持ち帰ったとも伝えられているし、全国学校栄養士協議会が1982年、学校給食にちなんで、1月22日を「カレーの日」に制定してもいます。
 「最初」や「記念日」は、カレーライス、ライスカレーの世界になると様々なアピールが出てきそうです。これを競っていてはきりがないので「みんな違ってみんな良い」で済ませる方が無難です。それより大変なのは、これを食す人々の好みの数だけカレーの味も千差万別。つくばーど®行事でも主たる献立にライスカレーを採用していますが辛さをどうするんだ?が最初の課題でした。「それはもう学校給食のカレーで行きます」という英断がなされたのは目からうろこな逸話でした。
「最初」や「記念日」は、カレーライス、ライスカレーの世界になると様々なアピールが出てきそうです。これを競っていてはきりがないので「みんな違ってみんな良い」で済ませる方が無難です。それより大変なのは、これを食す人々の好みの数だけカレーの味も千差万別。つくばーど®行事でも主たる献立にライスカレーを採用していますが辛さをどうするんだ?が最初の課題でした。「それはもう学校給食のカレーで行きます」という英断がなされたのは目からうろこな逸話でした。
 途中、途切れることもありますが、つくばーど®でカレーを振舞った最初の行事は2000年4月のことで、つくばーど®行事としては3回目でした。このときは最初の課題を抱えたままで「どんな味でも受け付けるカレーコンペでやるぜ」と見切り発車。ここで優勝したのが、この後カレー部門の板チョーとなるSIDEKICKさん作の学校給食カレーです。四半世紀前ですから家族連れのお子さんも小さかった。激辛カレーは自然と遠のいていったのです。
途中、途切れることもありますが、つくばーど®でカレーを振舞った最初の行事は2000年4月のことで、つくばーど®行事としては3回目でした。このときは最初の課題を抱えたままで「どんな味でも受け付けるカレーコンペでやるぜ」と見切り発車。ここで優勝したのが、この後カレー部門の板チョーとなるSIDEKICKさん作の学校給食カレーです。四半世紀前ですから家族連れのお子さんも小さかった。激辛カレーは自然と遠のいていったのです。
 つくばーど®行事の最初は1999年で、まあ何をやればいいか要領がわからず、一般的なバーベキューを設営しました。ここから試行錯誤して「何処そこで開くつくばーど®は〇〇」という具合に献立が決まっていき、カレーはほぼ、天狗の森で開いた行事か、天竜川河川敷に特化していきました。僕個人はSIDEKICKさんに敬意を表し、つくばーど®行事でカレーが作られるまでは家庭でも外食でも食わなかった時期がありました。現在、カレーは食いたいけれど控えねばならないのが信条的にきつい。
つくばーど®行事の最初は1999年で、まあ何をやればいいか要領がわからず、一般的なバーベキューを設営しました。ここから試行錯誤して「何処そこで開くつくばーど®は〇〇」という具合に献立が決まっていき、カレーはほぼ、天狗の森で開いた行事か、天竜川河川敷に特化していきました。僕個人はSIDEKICKさんに敬意を表し、つくばーど®行事でカレーが作られるまでは家庭でも外食でも食わなかった時期がありました。現在、カレーは食いたいけれど控えねばならないのが信条的にきつい。
負うた部下に教わる20周年
 「雷蔵さんっ、仙七のカレーぬれやき煎買って送ってー」(仙台)
「雷蔵さんっ、仙七のカレーぬれやき煎買って送ってー」(仙台)
ばかやろー、通販でだって買えるじゃねーかよ。と気が付いた時にはすでに真壁のお店で買い物をして発送も頼んでしまったのですが、行かなければ知りませんでした煎餅屋仙七さんって、前身の創業者を別にすれば、今の屋号で三代目さんが看板を上げて20年目なんだとか。「三代目で20年」というところにエスクードつながりがあります。仙七は初代のお名前です。
ついでに小分けしたやつも自宅用に買っていこうと「つくばの小路」を注文しました。僕はぬれ煎餅が苦手なので、小腹ふさぎにはこれくらいがちょうどよいのです。この秋には八郷(石岡市)と真壁(桜川市)を結ぶ上曽トンネルも開通するので、つくばーど基地からだと交通難所の上曽峠をパスして真壁まで15分は近くなります。
美味しいならもう何でも有り
 ここ何年も「 全国の飲食店向けに「うまいもん認定」事業を行っている一般社団法人・全日本うまいもん推進協議会が制定」という話題が5月22日になると出てくるのですが、5月をたま(0)ご(5)、22日をニワトリ(2) ニワトリ(2)のなんとも強引な語呂合わせから「たまご料理の日」として本日があてがわれているそうです。例によって「いつ制定されたんだよ」という記述がなかなか見つからないうえ、全日本うまいもん推進協議会がよくわからない。
ここ何年も「 全国の飲食店向けに「うまいもん認定」事業を行っている一般社団法人・全日本うまいもん推進協議会が制定」という話題が5月22日になると出てくるのですが、5月をたま(0)ご(5)、22日をニワトリ(2) ニワトリ(2)のなんとも強引な語呂合わせから「たまご料理の日」として本日があてがわれているそうです。例によって「いつ制定されたんだよ」という記述がなかなか見つからないうえ、全日本うまいもん推進協議会がよくわからない。
探しているうちに今度は一般社団法人 日本たまごかけごはん研究所というのがでてきて、ここが「たまご料理の日」についても触れているのだけれど、もうなんというかたまご関係記念日の多いこと!
 それはともかく同団体、「たまご料理の日」では食文化の啓蒙としてあらゆるジャンルにまたがる卵をとりあげる一方、食中毒撲滅といった目標を掲げていて、「たまご料理NO1グランプリ」なんていうイベントも開いているようです。世の中には卵にアレルギーを持つ人もいることはいますが、確かに日常食生活で卵と出会わないケースは少ないと言えるのかも。あっ、しまった22日はアポロ10を書こうと思っていたのに卵料理に行っちゃったよ。
それはともかく同団体、「たまご料理の日」では食文化の啓蒙としてあらゆるジャンルにまたがる卵をとりあげる一方、食中毒撲滅といった目標を掲げていて、「たまご料理NO1グランプリ」なんていうイベントも開いているようです。世の中には卵にアレルギーを持つ人もいることはいますが、確かに日常食生活で卵と出会わないケースは少ないと言えるのかも。あっ、しまった22日はアポロ10を書こうと思っていたのに卵料理に行っちゃったよ。
限定には弱いのよー。
「ふじさんミュージアム行ってみたいです」と
富士吉田の道の駅まで。
(ふじさんミュージアムは道の駅のすぐ近く)
どうせなら吉田のうどんも食べたいなと
新月サンがプリントアウトしてくれた一覧が
なんと〝2015年版〟(どこから引っ張ってきた?!)
じゃあココと電話番号入力したお店は既に無く、
ほかのお店探してぐーるぐる。
見つけたお店に閉店20分前に滑り込みました(笑)
(ふじさんミュージアムへ行ったのはその後)
で、富士山レーダードーム館も見学。
山頂の温度が体験できるというので、寒い方に
チャレンジ。
悪天候のスキー場なんて可愛いモンだと思える
くらいにめっちゃ寒かったデス・・・
職人の感覚
 笠間市の郊外で十割そばを出している「そば家和味(なごみ)」は、11時30分の開店時間にたどり着いてもすでに満席という人気店です。どうも蕎麦通さんたちには、蕎麦なら十割という傾向があるのかもしれない。そうでもないよー、というより、あぁこれはうまいと頬張れた十割蕎麦にほとんどめぐり合ってこなかった僕が不幸なのが、むしろそうなんだろうなあと感じていました。が、ここの蕎麦は上品で「これはいいですね」と舌鼓を打つことができました。
笠間市の郊外で十割そばを出している「そば家和味(なごみ)」は、11時30分の開店時間にたどり着いてもすでに満席という人気店です。どうも蕎麦通さんたちには、蕎麦なら十割という傾向があるのかもしれない。そうでもないよー、というより、あぁこれはうまいと頬張れた十割蕎麦にほとんどめぐり合ってこなかった僕が不幸なのが、むしろそうなんだろうなあと感じていました。が、ここの蕎麦は上品で「これはいいですね」と舌鼓を打つことができました。
 面白いのは天ざるの天ぷらが野菜系でまとめられている中、一品はその時期に合わせて何かしらの果物を揚げていることです。季節感はさておきこの日はリンゴの天ぷらでした。いずれの野菜天ともさくさくの食感を味わえるのに対して、リンゴはしっとりしていることと温められて甘酸っぱさがマシマシ。天ぷらは塩で合わせるのですが、リンゴ天だけは塩を使う必要がありません。蕎麦打ちもそうなのでしょうけど、職人の感覚が極まっているなあと思わされました。
面白いのは天ざるの天ぷらが野菜系でまとめられている中、一品はその時期に合わせて何かしらの果物を揚げていることです。季節感はさておきこの日はリンゴの天ぷらでした。いずれの野菜天ともさくさくの食感を味わえるのに対して、リンゴはしっとりしていることと温められて甘酸っぱさがマシマシ。天ぷらは塩で合わせるのですが、リンゴ天だけは塩を使う必要がありません。蕎麦打ちもそうなのでしょうけど、職人の感覚が極まっているなあと思わされました。
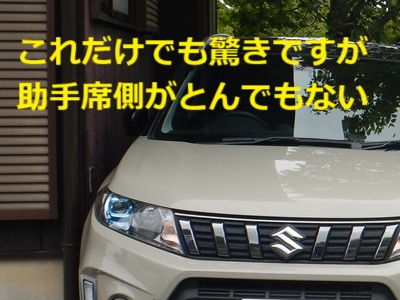 ここの主人、四代目エスクードに乗っています。車体の大きさの割に排気量小さいなと感じたそうですが、試乗したらターボの効果が納得できるレベルなことと、車体色が気に入っての購入だったそうですが、「この車の車幅がうちの駐車スペースギリギリなんですよ。よそのSUVだと入れられなくて」という意外な答えも。まあ一見の価値があるというか、これも職人の感覚かなあ。僕ならまず無理です。初代でも(僕は)無理。ハスラーでも(僕には)無理。
ここの主人、四代目エスクードに乗っています。車体の大きさの割に排気量小さいなと感じたそうですが、試乗したらターボの効果が納得できるレベルなことと、車体色が気に入っての購入だったそうですが、「この車の車幅がうちの駐車スペースギリギリなんですよ。よそのSUVだと入れられなくて」という意外な答えも。まあ一見の価値があるというか、これも職人の感覚かなあ。僕ならまず無理です。初代でも(僕は)無理。ハスラーでも(僕には)無理。
だーれも知らない知られちゃ・・・いけないのか?
 あっちこっちのうんちくサイトが「5月6日はコロッケの日」とぶちかましていながら、ほぼ異口同音に「コロッケなどの冷凍食品を製造する株式会社味のちぬやが制定」と紹介しているのですが・・・
あっちこっちのうんちくサイトが「5月6日はコロッケの日」とぶちかましていながら、ほぼ異口同音に「コロッケなどの冷凍食品を製造する株式会社味のちぬやが制定」と紹介しているのですが・・・
それっていつのことなんですか?
この疑問に答えてくれるところが、探し方が悪いのか、どこにもない。いよいよ困って(困るほどのことか?)、制定を認証した日本記念日協会で検索しましたよ。すみませんが興味のある人は「日付」かキーワード「コロッケ」でやってみてください。
出てきたのがこれ。
各種の冷凍食品の製造販売を手がけ、全国の量販店、コンビニ、外食産業などに流通させて、日本一のコロッケメーカーを目指す香川県三豊市の株式会社「味のちぬや」が制定した日。日付は明治時代に登場して以来、庶民の味方として親しまれてきたコロッケを春の行楽シーズンに家族で食べてもらいたいとの願いと、5と6で「コロッケ」と読む語呂合わせから。
なんということか、申請日も制定日も記されていません。
なんだよー・・・と、元々の味のちぬやさんのサイトに行ってみましたが、
やっぱり語呂あわせなのかっっっ
てことで制定された年次のことはもういいや。味のちぬやさんのコロッケではなく、我が家でこのところ気に入っているのは「かつや」の『じゃがいもがうまいポテトコロッケ』(写真)です。









