包丁のキレが悪くなってきたので研ぎに。 毎回毎回6本持ち込むので、お店の人も何となく覚えてた模様(笑) 年末とかならまとめて持ってくる人も珍しくないけど、来る度6本ってのは なかなか居ないらしいです。
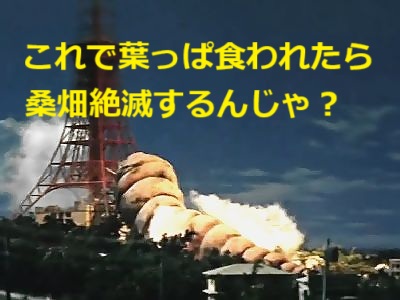 小満の初候、「蚕起食桑」が巡ってきました。蚕が桑の葉をぱりぱりと食べ始めるという意味で、路傍のニガナがよく茂ると謳った中国の「苦菜秀」とは趣を異にする、日本独自の文化を表現しています。養蚕の起源も中国ですが、日本でも弥生時代にまで遡る産業技術です。今では作付け面積が大幅に減りましたけど、幼稚園や小学校への通学路が、桑畑の中を通る町道というくらい、近所では盛んな「お蚕様」でした。
小満の初候、「蚕起食桑」が巡ってきました。蚕が桑の葉をぱりぱりと食べ始めるという意味で、路傍のニガナがよく茂ると謳った中国の「苦菜秀」とは趣を異にする、日本独自の文化を表現しています。養蚕の起源も中国ですが、日本でも弥生時代にまで遡る産業技術です。今では作付け面積が大幅に減りましたけど、幼稚園や小学校への通学路が、桑畑の中を通る町道というくらい、近所では盛んな「お蚕様」でした。
 島崎藤村や高田郁は、この蚕が桑の葉を食す音を「驟雨のよう」といった表現で綴っています。今の僕だと「驟雨ではなく甘雨じゃないかなあ」くらいのことは言えますが、子供のころの記憶だとまさしく蚕棚のある土蔵のなかで耳を澄ましていると、静かな雨の降るそれに似た響きがいつまでも伝わってきて、その薄暗い空間に「いる」途方もない数の蚕を想像して怖くなったものです。5月も下旬になり、いろいろなものの活力が満ちていくのも昔のままです。
島崎藤村や高田郁は、この蚕が桑の葉を食す音を「驟雨のよう」といった表現で綴っています。今の僕だと「驟雨ではなく甘雨じゃないかなあ」くらいのことは言えますが、子供のころの記憶だとまさしく蚕棚のある土蔵のなかで耳を澄ましていると、静かな雨の降るそれに似た響きがいつまでも伝わってきて、その薄暗い空間に「いる」途方もない数の蚕を想像して怖くなったものです。5月も下旬になり、いろいろなものの活力が満ちていくのも昔のままです。