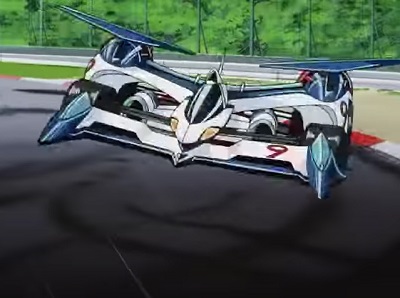正体を知られたら地球を去らねばならない。えっ、聞いてませんよそんな掟! というウルトラマンAこと北斗星司に課せられた運命は、実に過酷な結末でした。北斗は異次元人ヤプールの罠にかかり、信頼感を奪い取られた少年たちに「やさしさを失わないでくれ」と願うがために、正体を明かさざるを得ませんでした。これは北斗=Aが守ってきた対象にいとも簡単に「信じないぞ」と手のひらを返され、自らの無力さを突き付けられたとも受け止められるのです(尺の関係で後述)
正体を知られたら地球を去らねばならない。えっ、聞いてませんよそんな掟! というウルトラマンAこと北斗星司に課せられた運命は、実に過酷な結末でした。北斗は異次元人ヤプールの罠にかかり、信頼感を奪い取られた少年たちに「やさしさを失わないでくれ」と願うがために、正体を明かさざるを得ませんでした。これは北斗=Aが守ってきた対象にいとも簡単に「信じないぞ」と手のひらを返され、自らの無力さを突き付けられたとも受け止められるのです(尺の関係で後述)
 一方、初代以来久々に「ウルトラマンと決別」した東光太郎は、ウルトラマンタロウがいてくれれば、と他力本願となり自立の道を閉ざしていた少年に、「俺はもうウルトラのバッジには頼らない」と断言してその力を放棄し、地球人として異星人を退けました。自分の道は自身で歩んでいくというメッセージは、初代において科学特捜隊が悟ったそれと同一のものでした。光太郎は雑踏の中、何処かへ旅立っていくのですが、歴代で最も能動的、希望に満ちた「じゃあね」でした。
一方、初代以来久々に「ウルトラマンと決別」した東光太郎は、ウルトラマンタロウがいてくれれば、と他力本願となり自立の道を閉ざしていた少年に、「俺はもうウルトラのバッジには頼らない」と断言してその力を放棄し、地球人として異星人を退けました。自分の道は自身で歩んでいくというメッセージは、初代において科学特捜隊が悟ったそれと同一のものでした。光太郎は雑踏の中、何処かへ旅立っていくのですが、歴代で最も能動的、希望に満ちた「じゃあね」でした。
 「 地球の為にお前は戦い勝たなければならない。だが、お前自身が宇宙人という事を人間達に知らせてしまう事になる。 お前自身が本当に試される時が来たのだ」
「 地球の為にお前は戦い勝たなければならない。だが、お前自身が宇宙人という事を人間達に知らせてしまう事になる。 お前自身が本当に試される時が来たのだ」
おゝとりゲンの夢枕に立つウルトラセブンの言うことがまた唐突なんですが、ゲンがどうしたかというと、自分のことより同居していた少年・透の将来を案じて「自分の力で立つんだ」と諭します。セブンにしごかれてきたウルトラマンレオには、他者を思いやる心が宿っていました。
 結果、ゲンは周囲の人々から信頼され、地球を第二の故郷として生きる道を得るのですが、やさしさが他者の危機を見過ごせない。怪獣化しかかった少年を助けるためにレオの力を使わざるを得ず、ここでまた「正体を知られたら去らなくてはならない」妙な掟を肩代わりすることになります。この掟は本来、おとめ座から来た魔法使い卒業試験中の「コメットさん」にふりかかっていた問題で、しかもコメットさん、タロウを頼りにしたのに、ゲンが少年を救うのでした。
結果、ゲンは周囲の人々から信頼され、地球を第二の故郷として生きる道を得るのですが、やさしさが他者の危機を見過ごせない。怪獣化しかかった少年を助けるためにレオの力を使わざるを得ず、ここでまた「正体を知られたら去らなくてはならない」妙な掟を肩代わりすることになります。この掟は本来、おとめ座から来た魔法使い卒業試験中の「コメットさん」にふりかかっていた問題で、しかもコメットさん、タロウを頼りにしたのに、ゲンが少年を救うのでした。
「やさしさを失わないでくれ」「たとえその気持ちが何百回裏切られようとも」というウルトラマンAの最後の言葉(途中省略)は、Aの力を与えられた北斗にとっても、TAC入隊直後の隊内での仕打ちや、偽物の郷秀樹と対峙した時の坂田次郎との葛藤など、身をもって経験してきた辛さの表れのような気がします。それらを当初は南夕子が支えていましたが、夕子にもまた彼女の事情があり別れ別れにならなければならなかった。大いなるAの力をもってしても、運命は変えることができない。それでも北斗は地球の子供たちに「心」を託したかったのだと思われます。
ウルトラマンタロウというドラマは、ウルトラの名を借りたお伽噺でした。だからこそいろいろと破天荒な展開は許されるのですが、どんなお伽噺にも結末があり、本を閉じたときその世界は終わるものです。いつまでもウルトラの力に依存しては、未来の自分自身の世界を切り拓けない。東光太郎はそのことを少年に伝えたかったのでしょう。ウルトラマンと決別し、自ら異星人を撃退するという行動は初代から80までの歴代でただ一人の主人公です。
ウルトラマンレオは、いわゆるМ78星雲の種族とは異なり、獅子座の母星を滅ぼされ地球に逃げ延びていた亡命者です。その頃地球はウルトラセブンが防衛派遣されていたので、割り切ってしまえばセブンの戦いに加担する義理はなかった。彼はむしろ第二の故郷としてすがりたかった地球のためにセブンの意志を受け止め、いろいろひどい目に遭うのです。艱難辛苦を乗り越えて、ようやくその思いを成し遂げられたというのに、まさか別の番組でやさしさと引き換えに地球を去ることになろうとは。しかもですよ、コメットさん(大場久美子版)の初恋の相手はウルトラマンタロウだという・・・
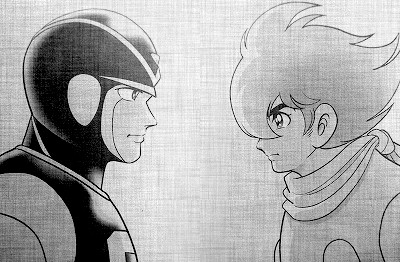 医者にかかる前に読んでいました「8マンvsサイボーグ009」。両者、原作者が「幻魔大戦」においてどちらが真の原作者なのかのトラブルを引き起こした経緯があるだけに、平井さんも石ノ森さんも、あの世で「こりゃー困ったカードだねえ」などと苦笑いしていそうな連載開始です(と思っていたら、桑田二郎さんまでもが鬼籍に入っちっゃた)。ついでに言うと、地底帝国ヨミ編で009を心中完結させているファンの神経を逆なでしそうな第1話という感じです。
医者にかかる前に読んでいました「8マンvsサイボーグ009」。両者、原作者が「幻魔大戦」においてどちらが真の原作者なのかのトラブルを引き起こした経緯があるだけに、平井さんも石ノ森さんも、あの世で「こりゃー困ったカードだねえ」などと苦笑いしていそうな連載開始です(と思っていたら、桑田二郎さんまでもが鬼籍に入っちっゃた)。ついでに言うと、地底帝国ヨミ編で009を心中完結させているファンの神経を逆なでしそうな第1話という感じです。