暑いので、冷たい麺を夕飯にしました。 ナスとピーマンが採れ始めたし♪ 先週貰い物のナスとピーマンで一度作ったら 意外と美味しかったので、我が家産で再び。 ナスもピーマンも旨ー♪
面白いことに、この駐車場に入ってきた車のドライバーがいちいち見に来るという(笑)
えっ、和邇さんこれ買ったの⁉と思ったけど、ナンバー(登録地)が違ってますが・・・まさかの隠し玉とか⁉
あーわかったわかった新帝国め! それ以上ここで暴露するなっ
ところでサイズ感と言えば。
全長×全幅×全高 3890×1645×1725mm
室内長×室内幅×室内高 1910×1275×1200mm
最小回転半径5.7m
ホイールベース2590mm
車両重量1190㎏
というのがジムニーノマド。一方エスクードノマドはというと
全長×全幅×全高 3975×1635×1700mm
室内長×室内幅×室内高 1680×1310×1280mm
最小回転半径5.4m
ホイールベース2480mm
車両重量1180kg
どちらも4速AТの数値です。まあまあたいして変わらないんですよ。乗車定員の差が室内幅に現れていますが、ジムノマのこのホイルベースと室内長は、幅の分に対するアドバンテージを意識しているんじゃないかと思ってしまいます。それにしてもテンロクノマドって、ショートに対して大きくなった感がはっきりしていましたけど、意外と軽かったんですよ。
 スズキ側のeVITARAとトヨタに供給されるアーバンクルーザーが事実上の兄弟車であることはすでに周知されていますが、ほぼ同一の車体ながら、前者がイギリスで2万9999〜3万7799ポンドで、オランダで先行している後者が約3万3000ユーロと、円にしたら700万とか500万とかを軽々と超えるクルマ。こいつらが黎明期のBEVだからという宿命なのか。頭の中にこびりつく車名が過去のもので、そんなタマかよって言いたくなるんだけれど。
スズキ側のeVITARAとトヨタに供給されるアーバンクルーザーが事実上の兄弟車であることはすでに周知されていますが、ほぼ同一の車体ながら、前者がイギリスで2万9999〜3万7799ポンドで、オランダで先行している後者が約3万3000ユーロと、円にしたら700万とか500万とかを軽々と超えるクルマ。こいつらが黎明期のBEVだからという宿命なのか。頭の中にこびりつく車名が過去のもので、そんなタマかよって言いたくなるんだけれど。
そのBEVとしてのメーカー保証が、両社ともディーラーでの点検整備を条件として「最長10年か、走行距離96万キロまでバッテリー容量の70%以上を保証」という顧客への信頼獲得と囲い込み対策を用意しているようです。
すごいなあ。少なくともスズキの四駆に乗って40数年、96万キロ保証なんて言葉は聞いたこともありません。搭載されるバッテリーの品質がどれほどのものかは未知数だけど、それくらいのことをやらなければ欧米でのシェア争いには太刀打ちできないのかもしれない。しかし10年乗る人は確実にいるとして、96万キロ走らせるユーザーって、海の向こうならば当たり前なんでしょうか。
いずれ両車とも日本国内でもリリースされるなかで、96万キロって誰も本気にしないんじゃないかと、実際に走らせた人間としては感じてしまいます。
 今日が、ということではなく、今日が「雷記念日」なんだけれどそのことは何年も前に「雷/THUNDER」で書いてしまったので別の話を。
今日が、ということではなく、今日が「雷記念日」なんだけれどそのことは何年も前に「雷/THUNDER」で書いてしまったので別の話を。
大気が不安定となって雷が三日ほど続くとすれば、それは梅雨明けの兆候。そのあと十日くらいは太平洋高気圧の張り出しでぐっと暑くなって晴天が夏をもたらすという古い迷信があります。
迷信とはいっても、天気の変化を読み取ってきた昔の人々の体験から云われだした、意外と根拠のある気象逸話だと思います。菅原道真の祟り噺などより、よほど科学的なのです。ただ、その時代と現代とでは地球そのものの温暖化が進行して、ものによってはもはや通じない迷信も出てくるのかもしれません。
昨年の梅雨入りが6月21日で、明けたのが7月18日ごろだったことからも、雷三日はもう少し先になるのでしょう。それでも今日から雷が三日続くようなことになれば、その後の十日で数えると7月8日あたりで関東の梅雨は明ける計算になりますね。
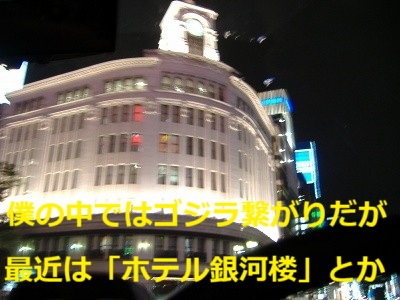 銀座四丁目において、服部時計店が営業を始めてから130年。現在の和光の前身であり。あのランドマークとなったモダンなビルは今なお健在です(今の時計塔ビルは1932年の完成で二代目)
銀座四丁目において、服部時計店が営業を始めてから130年。現在の和光の前身であり。あのランドマークとなったモダンなビルは今なお健在です(今の時計塔ビルは1932年の完成で二代目)
昼も夜も関係なく、この時計塔を撮ったり背景にしたりの人が増えているなあと思えば、アニメの方は最終回を迎える「アポカリプスホテル」のホテル銀河楼として認知度が上がっているのですね。
第一作目の「ゴジラ」は僕とは世代違いで、1984年版ゴジラは有楽町マリオンをぶっ壊しにくる途上、どう考えても四丁目をのし歩いていたはずです。が、和光に対しては一作目の無許可破壊(セットですけど)トラブルによって長いこと東宝も遠慮していたのか、次に時計塔が出てくるのは「シン・ゴジラ」と「-1.0」というのも意外でした。
 アポカリプスホテルの時代はずーっと未来の2157年。セイコーから買い取られてホテル改装されたのがいつのことかは不明ですが、銀座どころか地球規模で荒廃してしまう時代という設定に、怒られなかったのかと心配になります。その辺は許可の取り付けを澄ませているのでしょう。そんなことよりも、今の現場の人々が、敵を出さない、戦わない(全くではなかったけど)ロボットものを生み出すセンスに好感を持てました。それでいいんだと思います。
アポカリプスホテルの時代はずーっと未来の2157年。セイコーから買い取られてホテル改装されたのがいつのことかは不明ですが、銀座どころか地球規模で荒廃してしまう時代という設定に、怒られなかったのかと心配になります。その辺は許可の取り付けを澄ませているのでしょう。そんなことよりも、今の現場の人々が、敵を出さない、戦わない(全くではなかったけど)ロボットものを生み出すセンスに好感を持てました。それでいいんだと思います。
 で、こっちも大団円にたどり着きましたが、よくまあ一話分の尺にこれだけ詰め込んだもんだよという中身ながら、散らばっているものの多くは「正史の焼き直し」で、向こう側の世界はハイパー化をも促すバイストン・ウェルまで使いまわす始末。そういうところが鼻につく。だから「戦争の怖さを感じられない」と言われてもしょうがないんだけれど、だからこそ「まあどうにかなったか」ってところです。最後に出てくるビーチがキューバあたりだったら笑っちゃうけどね(わかる人にはわかる)
で、こっちも大団円にたどり着きましたが、よくまあ一話分の尺にこれだけ詰め込んだもんだよという中身ながら、散らばっているものの多くは「正史の焼き直し」で、向こう側の世界はハイパー化をも促すバイストン・ウェルまで使いまわす始末。そういうところが鼻につく。だから「戦争の怖さを感じられない」と言われてもしょうがないんだけれど、だからこそ「まあどうにかなったか」ってところです。最後に出てくるビーチがキューバあたりだったら笑っちゃうけどね(わかる人にはわかる)
と思ったら、ソロモン諸島のマキラ島に「キラキラ」という名の町が実在することを教えられました。しかも州都で海岸もあるんだって。
それはさておき何が言いたいかって、戦後80年になんなんとする今、その人々が描くアニメを「絵空事」などと言っていいのかと。いいじゃんそれで。戦前戦中の人々が巻き込まれてしまった苦渋の時代を、若い人たちに体験させてはならないのです。だったら戦記物とやらがイマジネーションの中でしか生まれないことは当然であって、世代間の乖離を自戒しても自慢してもいけない。ロボットを戦争の道具に仕立て上げてスポンサー喜ばせてきたオールドタイプが、それこそロボット出てくりゃ戦記物だって仕事を、いったいいつまでやらせるのよと。
 だから、GQuuuuuuXは僕みたいなおっさんが観ても「悪く無かった」。残念であるとすれば、それを「機動戦士ガンダム」の軸線上で仮想戦記としてやらなくてはならなかったことで、そのジレンマも理解できます。だから僕は次に来るものには秘かに期待していたい。偉い人たちが作ってしまう前に、21世紀の作り手はこんなことをやりたくて、大人の事情の壁を突き崩しているんですよと。
だから、GQuuuuuuXは僕みたいなおっさんが観ても「悪く無かった」。残念であるとすれば、それを「機動戦士ガンダム」の軸線上で仮想戦記としてやらなくてはならなかったことで、そのジレンマも理解できます。だから僕は次に来るものには秘かに期待していたい。偉い人たちが作ってしまう前に、21世紀の作り手はこんなことをやりたくて、大人の事情の壁を突き崩しているんですよと。