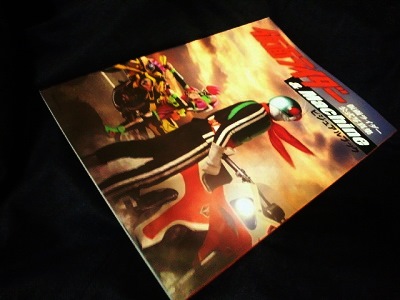何をいまさらな話のTDF‐UG(地球防衛軍・ウルトラ警備隊)について。ウルトラセブンの放送50周年にして未だに自分の中で腑に落ちないことがあります。彼らの極東基地は静岡県の富士山麓の地下数十メートルに所在すると言われていますが、これはどのくらい信憑性のある情報だったのか。基地全容を規模で考えれば、様々な部門のひとつやふたつは富士山麓にも展開していると思われますが、富士山麓というのはいったいどれくらいの範囲を示すものなのかが判然としないのです。
何をいまさらな話のTDF‐UG(地球防衛軍・ウルトラ警備隊)について。ウルトラセブンの放送50周年にして未だに自分の中で腑に落ちないことがあります。彼らの極東基地は静岡県の富士山麓の地下数十メートルに所在すると言われていますが、これはどのくらい信憑性のある情報だったのか。基地全容を規模で考えれば、様々な部門のひとつやふたつは富士山麓にも展開していると思われますが、富士山麓というのはいったいどれくらいの範囲を示すものなのかが判然としないのです。
 たとえばウルトラホーク1、2号の発射サイロとして偽装されている「二子山」はその富士山を遠望する位置にあり、なんとなく元箱根あたりからの風景にも見えます。実際に箱根町には二子山が存在しますが、あの山が発射サイロだったら東海道からも国道1号からも丸見え。駅伝のとき侵略者がやってきたらどうするんだ?という位置関係になります。第一、箱根町は神奈川県なのです。ここまで含めて富士山麓と呼んでしまうのはいささか乱暴ではないかとずっと感じていたのです。
たとえばウルトラホーク1、2号の発射サイロとして偽装されている「二子山」はその富士山を遠望する位置にあり、なんとなく元箱根あたりからの風景にも見えます。実際に箱根町には二子山が存在しますが、あの山が発射サイロだったら東海道からも国道1号からも丸見え。駅伝のとき侵略者がやってきたらどうするんだ?という位置関係になります。第一、箱根町は神奈川県なのです。ここまで含めて富士山麓と呼んでしまうのはいささか乱暴ではないかとずっと感じていたのです。
 ウルトラ警備隊の作戦室や格納庫類は、箱根の二子山かどうかはともかく、かなりの部門が神奈川寄りの配備なのではないか? クール星人が攻めてきたとき、防衛軍隊員が拉致されたのが極東基地の「すぐ近く」(ソガ隊員談)で、フルハシ・ソガが現場に駆けつけると、神奈川県警のパトカーが樹海一体を警邏しています。樹海と言ったら静岡どころか山梨県の青木が原ですが、そこにいたのは神奈川県警。富士箱根伊豆国立公園括りなら、警邏範囲に含まれる?(そんなばかな)
ウルトラ警備隊の作戦室や格納庫類は、箱根の二子山かどうかはともかく、かなりの部門が神奈川寄りの配備なのではないか? クール星人が攻めてきたとき、防衛軍隊員が拉致されたのが極東基地の「すぐ近く」(ソガ隊員談)で、フルハシ・ソガが現場に駆けつけると、神奈川県警のパトカーが樹海一体を警邏しています。樹海と言ったら静岡どころか山梨県の青木が原ですが、そこにいたのは神奈川県警。富士箱根伊豆国立公園括りなら、警邏範囲に含まれる?(そんなばかな)
 しかしサイロが湖の近くにある風景が芦ノ湖とも言いきれず、どこか秘匿されたエリアの人造湖と偽装山という説も考えられます。ウルトラ警備隊には現場急行用の地下ハイウエイ「シークレットロード」もあるし、静岡県富士宮市にも二子山はあるのですが、富士遠望のロケーションと神奈川県警の警邏という状況から、クール星人の襲った「すぐ近く」の現場は静岡ではないような気がします。これこそが情報を開示しているようで巧みに攪乱している地球防衛軍の狡猾さなのでしょう。
しかしサイロが湖の近くにある風景が芦ノ湖とも言いきれず、どこか秘匿されたエリアの人造湖と偽装山という説も考えられます。ウルトラ警備隊には現場急行用の地下ハイウエイ「シークレットロード」もあるし、静岡県富士宮市にも二子山はあるのですが、富士遠望のロケーションと神奈川県警の警邏という状況から、クール星人の襲った「すぐ近く」の現場は静岡ではないような気がします。これこそが情報を開示しているようで巧みに攪乱している地球防衛軍の狡猾さなのでしょう。