そうでもなかったダイアモンドリリー。 本当に遅い年は11月末に咲いてました。 (いくらなんでもこれは遅すぎ) 後は大体10日前後だったので・・・ まあ我が家的には平均的な開花時期かしら。
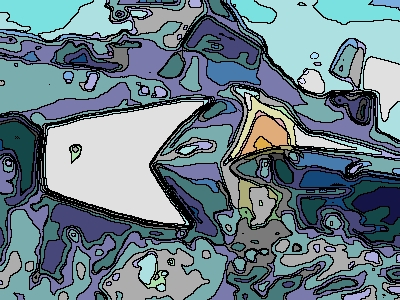 「着水する、衝撃に備え!」
「着水する、衝撃に備え!」
源田が叫ぶ。天田は上空警戒を進めながら高速粒子ビームを撃たれた場合の対処を巡らせる。
「しかしなんだって船体の直接破壊を狙ってこない?」
「太陽光プラズマからの蓄電、40%消費。潜航すると太陽光集積はできません。もっともまだ夜明け前か」
服部が機関制御を続ける。
「3射目が来ます! 前方1キロ未満に着弾っ」
光芒が闇を切り裂いた。MJ号の着水進路が沸騰し相転移を始めた。
「源田、そのまま海中に突っ込め! おそらく『熱い氷』は海面付近だけでそう厚くはならない」
「隊長の勘を信じますよ! 艦首トリム45度で海面突入!」
「隊長、こんなときですけど本部から暗号受電してます」
マリが当に報告するが、海面突入の衝撃で座席から放り出されそうになり、当も必死にシートに背中を押し付ける。MJ号の水押し(みおし)が固体化していく海面を切り裂き巨大な艦体を沸騰する波にめり込ませた。この衝突衝撃は艦体のキールが受け止めるが艦内は上下左右に揺さぶられ続ける。両翼がもぎ取られるのではないかと、さすがの天田も一瞬の不安をよぎらせる。
冷却剤タンクの融解作業中だった村上と寺川も、作業中の機材事弾き飛ばされてしまう。幸いにも重量のある機材に押しつぶされることはなかったが、二人ともそれなりの打撲を負った。厚手の対放射線防護服を着ていなかったら、打撲程度では済まなかったかもしれない。
「なんて荒っぽい着水をするんだ!」
「怪我はないか寺川君、機材は今のでおしゃかになった」
「どうしますか。まだ融解が終わっていません」
村上は少し逡巡して意を決したように告げる。
「ブリッジに戻って奥の手を使う。しかし蓄電池の容量も使い切るかもしれん」
「でも融合炉が使えるようになりさえすれば」
「そういうことだ。だがもう一度プラズマ生成するまでには時間がかかる。急ぐぞ」
安定を欠いたまま、MJ号は海中に飛び込んだ。主翼は両舷とも大きな軋み音を立てた。当然ブリッジには危険度合いを超えたという警報が鳴り響く。艦体損傷ぎりぎりの勢いだったが自動姿勢制御システムがかろうじて源田の操舵するコースに乗せていく。両翼とも損壊はしなかった。
「メインタンク全速注水。深度200で索敵する」
「例のビームは」
天田の懸念を当が払拭するように言う。
「いかに『熱い氷』でも瞬時にこの深度まで凍らせられるとは思えん。それに海中には奴らの仲間がいる。もろとも凍らせては作戦の意味がない」
「しかし奴らが網を張っているということは・・・そうか、MJ号を生け捕りにしようって魂胆なのか」
天田は拳を握り締めた。
「ソナーに感。10キロ四方に潜水艦らしき反応を三つ確認。この音紋はディーゼル潜ですね」
「Qにしては意外な兵力だな。こっちの位置も探知されているよな」
「スクリューどころか動力音も打ち消していないなんて、馬鹿にされてるみたいです」
マリは操作盤とモニターを凝視しながら報告する。
「あ、忘れちゃいけなかったです。さっきの電文、本部のエマさんからです」
「なんと言ってきてる?」
「隊長親展の暗号伝聞です。そちらに転送します」
当の席のコンソールにひと際明るい明滅が生じた。当はキーボードを叩いて指定暗号を入力する。ややあって電文が当のモニターに投影された。
「・・・今送ってきてどうしろと言うんだ!」
「何事ですか?」
天田が振り返って聞くのを見ながら、当は「こっちに来い」と手で合図した。それを了承とみなした天田は当の席のモニターをのぞき込んだ。
「・・・へっ、呑気なもんだ。齢百を超えると肝のすわり方も超人ですね」
「とにかくこの場を脱出せねばならん。会長の言う『elfter Schwarzer』とやらを警戒するにも生き残らねば何も出来ん」
「しかしこの『elfter Schwarzer』とはいったい?」
「今は考えるな。まず目の前の敵を殲滅する。源田、使える武装はどれだけある?」
不意に問われながらも源田は操舵を止めずに即答した。
「ミサイル、砲弾はまだ一発も撃てていません。魚雷も然り。あとは『ビッグ・エム』があります。主砲はまだ使えません。レーザー・ビーム発射器は海中じゃ用無しですが炉の復旧待ちです」
「『ビッグ・エム』の使用は外しておこう。伊豆・小笠原海溝に誘い込む。この進路でどのくらいで行ける?」
「約15分。しかし電力が気になりますね。既に省電力モードで動かしてますが、あれから早くも7%使っちまいました」
「その気になる残電力なんだが、イチかバチかの打席に立たせてもらえないだろうか」
村上と寺川が戻ってきた。二人とも放射線防護服を着たままだが被ばく量はほとんどなく、ブリッジのモニタリング警報は沈黙している。これを脱ぎもせず汗だくの村上から当に提案が申告される。
「隊長も知ってのとおり、昨年の大型改修でMJ号の主機は原子力機関から核融合機関に換装された。これによって太陽光プラズマエンジン全体がシステムとして完成した形になる」
「だが炉がまだ復旧していない」
「ゲンさんが悪いわけではないが、この着水潜航の衝撃で超音波融解装置が破損してしまった。もう悠長なことをしていられないから奥の手を打ちたい。太陽光プラズマユニットに付け加えられた超高電圧レーザー発振器を使って落雷を起こす」
「・・・どうなる?」
「強力な電気マッサージで『熱い氷』を粉砕する。これには融合炉の発振器を冷却タンクに移設せねばならんが、それができれば中のヘリウムを刺激して冷却水の分子崩壊を誘発させられる。不幸中の幸いだが蓄電残量のすべてを使うわけにはいかんから、艦内誘爆するほどの電撃には至らない」
「発振器の付け替えにはどの程度かかる?」
「図面によれば発振器自体は三系統完備している。炉への回路二系統をいったんカットし、予備の外部ユニットにバイパスさせて冷却タンクのバルブに接続する。ここから遠隔操作で作業するから20分でどうにかできるだろう」
「バルブにということは、タンクを外部から電撃するということか」
「その通りだ。幸いバルブハッチの外径は発振器とほぼ同じ規格でハッチに被せられる」
艦内の主要区画は完全絶縁がなされているが、村上の言う放電撃の出力はオーバーロードを招くかもしれない。冷却剤タンクが融合炉とつながっている以上、炉の配管には幾ばくかの影響を受けるだろう。
だが・・・
当は本部から送られてきた暗号伝聞を思い返した。
Qによる衛星兵器の陽動疑念、解けていない固有名詞『elfter Schwarzer』。それらの連絡と共に送られてきた一文に、プラズマはもはや枯れつつあり使いこなせる技術とあった。その意味を考えるには時間がない。
当は「くそ親父め」とうめきながら決意した。
「細かいことは博士に任せる。15分で隔壁閉鎖と放電撃システムを立ち上げてくれ。海溝に敵を呼び寄せながら全弾を打ち尽くす。放電のタイミングはそれで計ってもらいたい。念のため全員絶縁作業着を着用!」
「エス・エム・ジェイ!」
村上の返答と同時に全員が持ち場につく。
「ゲンさん、いま先生を借りても大丈夫かな」
村上は源田に尋ねる。すかさず源田は「では寺川君と交代を」と応じる。
「先生、レーザー発振器の付け替えを始めるので手伝ってくれ。寺川君はそこから隔壁閉鎖と確認を頼む!」
村上は昨年の改装作業で一新されたブリッジの自席でコンソールパネルの一部を剥がし、しばらく覗き込んだ内部配線からこれだと見極めたコード数本のコネクターを外した。
英は村上が始めた作業をチラ見しただけで、手伝うべき内容を掌握した。彼はこの手の実作業も得意とする。
「これ、必要でしょ」
村上のところへやってきたとき、彼は既に自分のコンソールから「今は使わないだろう」と考えたレバーを二本、ボタン式スイッチ類をいくつか引き抜いて持ってきていた。
「さすが先生だ。回路図を書いている暇はないから、こことここに穴をあけてコネクターの受けとレバーを取り付けてくれないか。スイッチは適当な場所で構わない」
村上は剥がしたコンソールカバーをひっくり返し、マジックインキで印をつけると同時に、印の下に操作内容を示す書き込みをする。
英がそれを受け取り、工具箱のハンドドリルで作業を進める。村上は時計も見ずに黙々と回線を引き出し手渡していく。
「何をやってるんだ博士は」
彼らの様子を眺めていた当は多少怪訝な顔をするが、すぐに、発振器の移設操作系がブリッジには無いことに気づいた。
「深深度魚雷来ます! 9時方向から四本、距離8キロ!」
マリが叫んだ。威嚇だなと天田はつぶやき源田に指示する。源田の操艦でMJ号は潜航しつつ艦首を20度傾けた。
「左舷に加速用ハイパーポリマーを展開。直撃は防げる。ただ当たると炸薬の破裂圧力は海上より大きいぞ」
「深度550、現状でこれ以上の潜航は危険。トリム修正しま・・・」
源田の声が左舷からの衝撃にかき消される。魚雷がハイパーポリマーに絡めとられそのまま炸裂したようだ。
衝撃の度合いは予想よりもはるかに小さいが、バリアとなっていたポリマーの大部分は吹き飛ばされてしまう。
「妙だな。Qとて素人じゃあるまいに、この深度で当てるなら艦底を狙ってくるのが定石だ」
当は敵の性能をどう見るべきか多少戸惑った。
MJ号の深深度潜航能力は日本の海上自衛隊が保有してきた潜水艦を現在でも凌駕している。そもそも戦艦であり潜水艦であり航空機でもある万能艦は、少なくとも国連加盟国の何処にも存在しない。それでは無敵無双かと言えば否、なのだ。海中において艦底部の至近距離で魚雷が炸裂すれば、艦体下方では海水が炸裂圧力によって今しがたポリマーが排除されたように海水自体が吹き飛ばされ浮力を奪い取る。そうなれば自重約28000トンもの荷重が一気にMJ号のキールや外殻をへし折ろうとするだろう。
そんなことはサブマリナーの常識のはずだが、わざわざ水圧下で速度が落ち、回避されるような攻撃を仕掛けてくるのか。その迷いの無さが当の勘に触るのだ。
「まさか原潜そのものが自動操艦されているのか?」
※本作は勝手に書いているオリジナルです。同作関係者などとの関係はありません
いかん・・・長くなりすぎ。