 TDAのシーズンが幕を閉じ、来期に向けた助走が早くも始まっています。
TDAのシーズンが幕を閉じ、来期に向けた助走が早くも始まっています。
まず大きな出来事は、後藤誠司君が遂にエスクードから降りることとなります。10年めの今年は活躍を見られず残念でしたが、2009年からずっとTA51Wを走らせ、広い世界にエスクードの速さを見せつけてくれたことに感謝しなくてはなりません。
実は後藤君には、TA51Wの不調続きの折、奇策が示唆されていました。
まだ一部の中古車サイトに表示されていますが、競技用にパーツ換装されたTA01R、あのレジントップを島雄司社長自身が買い取っており、これを再整備してリミテッドクラスも制覇するという計画でした。ダブルタイトルをなぜ狙わせようとしたかについては、外の世界に彼を推し出すという声がかかっていたからです。
この計画は、現実に今シーズンを戦っていない以上白紙に戻されるのですが、後藤君にはリミテッドクラスへの参戦自体が壁となりました。それはまあ、誰が勝つかわからない、誰にでも勝てるチャンスがあるというリミテッドに、彼が出てしまったら、他のエントラントが敬遠することが分かったからだと、島社長も苦笑しています。
競技は参加者がいて成立しますから、打倒ウエストウインのためにハイパワーマシンを送り込んでくるアンフィニクラスは盛況ですが、入門編でもあるリミテッドに人が集まらなければ、TDAの意義にもかかわる問題となるのです。
 しかし、島社長は2台のエスクードを、どちらも退役させないそうです。ここへきて、後藤君と川添哲朗君の51Wと52Wを比較すると、車体と駆動系に関しては、51Wの方がダメージが少ないことが確認されました。川添君のTA52Wは、転倒の際に車体とエンジンマウント部その他各所が歪み、ドライブシャフトも正常位置に戻せず負荷をかければ抜けてしまう状態。エンジンだけが極上の音で回っているそうです。
しかし、島社長は2台のエスクードを、どちらも退役させないそうです。ここへきて、後藤君と川添哲朗君の51Wと52Wを比較すると、車体と駆動系に関しては、51Wの方がダメージが少ないことが確認されました。川添君のTA52Wは、転倒の際に車体とエンジンマウント部その他各所が歪み、ドライブシャフトも正常位置に戻せず負荷をかければ抜けてしまう状態。エンジンだけが極上の音で回っているそうです。
あ、そういうことか? と思ったら、短絡的に想像したこととは異なる話となりました。
「川添君はまだ52Wでやり残したことがあると主張しています。だから新しい車体を探しているところです。乗り換えで提供してくれる人がいらしたらぜひ紹介してください」
二代目2000ccのショートで5速マニュアル。これはややもすると初代のコンバーチブルを探すよりも困難を極めそうです。我々エスクード仲間でも過去に3台しか知人がいないほどですから、4速ATの個体でもやむなしで獲得し、ハンガースポーツあたりで寝かせてあるテンロクコンバーチブルのミッションでも移植するしかないかもしれません。
いずれにしても川添君のエスクードについては、大枠で直していく方針。運よく代替として同型車が手に入ればそちらに乗り換えるという展望で、話はまとまっています。
 それでは初代の2台をどうするつもりなのか。
それでは初代の2台をどうするつもりなのか。
「まず01Rをいじります。あれを投入してエスクード体制を維持している間に、51Wの修理と再セッティングを進めます。まあなにしろ資金無いチームなもんで、ほいほいとニューマシンを繰り出せません」
まだ目が離せません、ウエストウイン。その展開は次にでも。

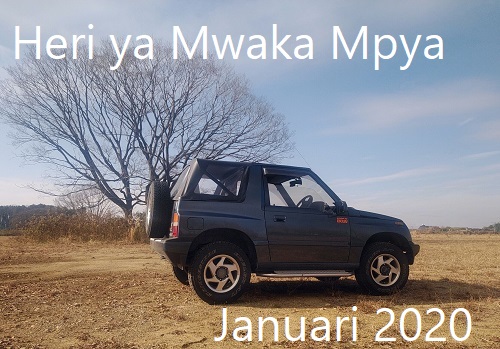




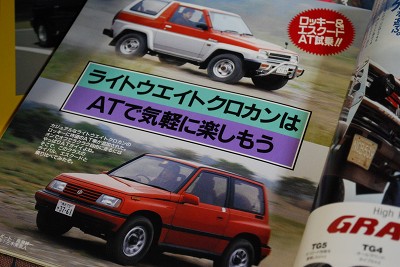








 1969年11月19日。その年の7月に成し遂げられたアポロ11号クルーによる人類初の月着陸が偉大過ぎたために、わずか4か月後に12号のクルーも月に降り立ったことはだいぶ霞んでしまいました。
1969年11月19日。その年の7月に成し遂げられたアポロ11号クルーによる人類初の月着陸が偉大過ぎたために、わずか4か月後に12号のクルーも月に降り立ったことはだいぶ霞んでしまいました。