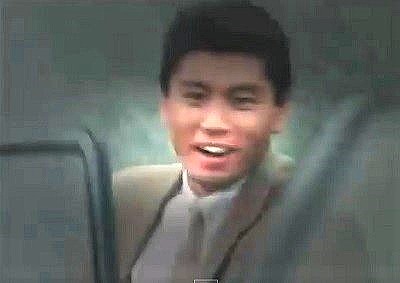ゆうきまさみさんが週刊少年史の連載を始める折、たぶん月刊ニュータイプあたりの連載コラムか何かで綴っていたことがあります。
今度、商業誌に書くことになってとメジャー誌デビューのことを言ったら、ファンの人から「〇○〇ですか」と聞かれ、それについて「メジャー誌って、どんな田舎の駅の売店でも買えるものだと思うんだけど」とつぶやいている展開でした。
詳細な記述なんか忘れてますが、だいたいそんな感じ。
その氏漫画家35周年企画という文芸別冊に至っては、発売2日めで仙台市内中の書店という書店に既に無いのか回ってこないのかのまるぼし状態で、結局注文したら第2版がやってきました。とあるかなり大手の書店の検索システムではこのムック自体がリストになかった(同誌の他の企画ものはラインナップされているのに)ところをみると、ノーマーク。うむむ・・・やっぱり一般的な知名度は低いのかと思いきやの重版出来ですから、何が何だかわかりません。
内容? こんなの漫画以上に面白いわけないじゃないですか(超問題発言)。アニパロデビュー時代から知っている作家だから、雑誌に載る対談やインタビューはいろいろとリアルタイムで読んできたし、その都度が面白かったのです。しかしそれは、その時そのときの連載がより面白かったからでもある。だから今回も連載の次に面白い。
とはいってもインタビューや対談を一読してみて、発言していることに昔とブレが無いところは実にほっとさせてもらえます。その辺は、別のムック、ゆうきまさみ年代記と読み合わせればわかります。だけど対談はともかく、3万字に及ぶというインタビューは、インタビューしている人が楽しみすぎで発言(文字数)多すぎ。ところにより本人のコメントの方が短いんだもの。
そして偉大なる予告ですが、あと5年後の漫画家生活40年めにこの手の企画が実現する場合、30年の時に描いている「究極超人あ~る」の続きを描きたいそうです。続くんですか、あの話!