 木場のあたりで永代通りからタクシーに乗りました。なぜ東西線を使わないのよと言われれば、まあ行き先がそっちじゃないんだけど永代橋を渡りたいのだという欲によるものです。
木場のあたりで永代通りからタクシーに乗りました。なぜ東西線を使わないのよと言われれば、まあ行き先がそっちじゃないんだけど永代橋を渡りたいのだという欲によるものです。
永代橋と言えばですね、89年9月期にリリースされた初代エスクード2冊目のカタログ内に、ここを茅場町方面から走って来るハードトップのスチルが使われているのです。このカタログでもすでに写真合成は一部で始まっていますが、このシーンはもちろん多くが撮りおろしでした。
僕がエスクードの写真を撮り始めたとき、参考にしたのがこの版のカタログでしたが、自分で永代橋を走っちゃうと絶対にこのようなカットは撮れず、さりとて橋の上に駐車するわけにもいかず、未だにこれと同じものを撮ることができていません。
そういう思いもあって、今回はトラスのアーチくらい車窓から撮ろうかなと企んでいたのですが、タクシードライバー最短距離運行に忠実。なんと門前仲町で清澄通りに右折してしまうのでした!
 ええっ、と予想外の展開に翻弄されていると、タクシーは首都高9号線へ移動し、首都高下の墨田川大橋を渡るのです。むむっ、ということは車窓から大川端方面が見えるじゃん。そこには真横からの永代橋もあるじゃん。
ええっ、と予想外の展開に翻弄されていると、タクシーは首都高9号線へ移動し、首都高下の墨田川大橋を渡るのです。むむっ、ということは車窓から大川端方面が見えるじゃん。そこには真横からの永代橋もあるじゃん。
というわけで咄嗟に撮ってはみたのですが、完全に逆光だわ欄干が邪魔するわで、またしても徒労に終わるのでした。帝都の門(永代橋の俗称)はなんとも遠いなあ・・・

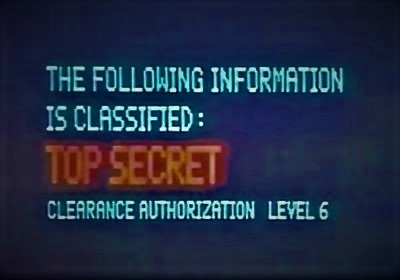
 見知らぬ人のツイッターで見かけた、「代車で乗ったMT車」というスチルの右端に、エスクード誕生20周年のときにkawaさんが夜なべして切り出してくれた記念プレートが。
見知らぬ人のツイッターで見かけた、「代車で乗ったMT車」というスチルの右端に、エスクード誕生20周年のときにkawaさんが夜なべして切り出してくれた記念プレートが。

















