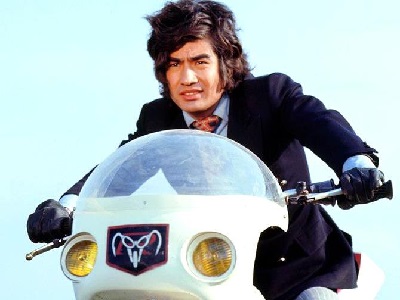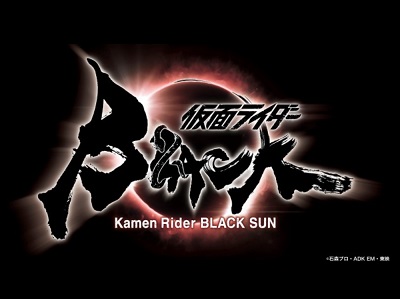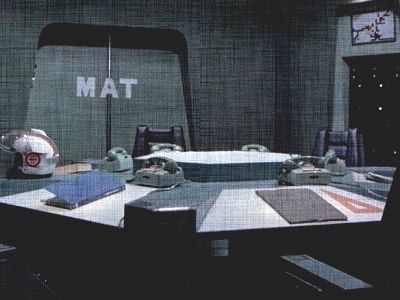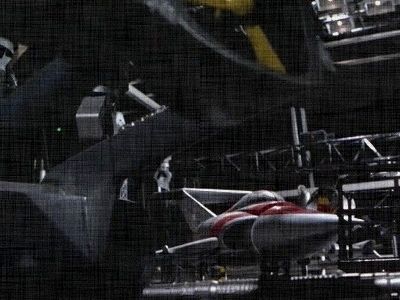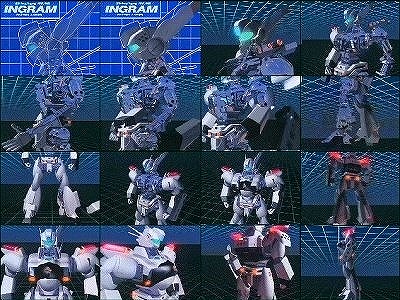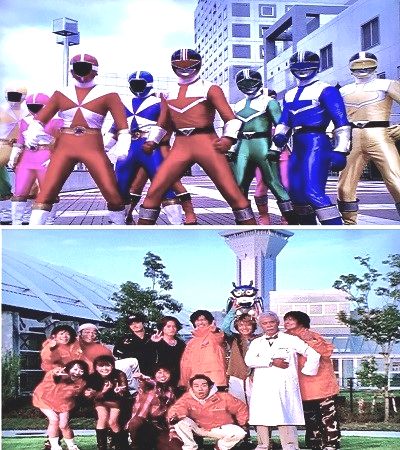「シン・仮面ライダー」の製作発表がなんとなく大きな話題になっている中で、この企画自体を知らされていなかった(とは思えないんだけれど)という島本和彦さんの、「仮面ライダー50周年お祝いイラスト」(のツイート)がなんとなくささやかに同情されているようです。曰く、「まるでアオイホノオな展開」。ということで、かつて「シン・ゴジラ」が封切られたときに、島本さんが叫んだ「やめろぉ庵野!!」の再現になってしまったと。しかも、ゴジラはともかく今回は仮面ライダーですから、そこに原作者とのパイプを築いていた島本さんにとっては青天の霹靂なのです(真実はそうでも無いと思うんだけれど)
だけど思い返しちゃいますよ。島本さんは昔、生前の石ノ森章太郎さんから「君に委ねるから描け」と言われて、仮面ライダーの原点とも言える「スカルマン」を漫画化して、ここに石ノ森キャラクターを総動員させていました。当然、仮面ライダーをモチーフとする人/バッタ融合型改造人間も繰り出しており、スカルマンとの激闘が描かれているのですが、今これを見ていると、「庵野ライダーに蹴りつけられている島本スカルマン」にしか見えない。
こうなったらコミカライズの権利をなんとしても獲得してもらって、コミケでは無く書店で発売できる単行本を描いていただきたいところです。
・・・それか? 映画の公開がコロナ禍で遅れて2023年3月っていう半端な段取りなのは、実はコミカライズの契約も動いていて、執筆時間を割いての予定調和???(それはそれで監督の手のひらの上で踊らされちゃうという)